先週の金曜日と今日、図工の同僚や国語科の同僚と表現全般や作文の授業のあり方について話し合う機会があり、これからより考えてみたい課題も見つかった。それは「書き手としての自分」と「教え手としての自分」にどう橋を架けるのかという課題だ。これは、すぐにどうこうなる問題ではないのだけど、忘れた頃に思い出すために、ここに書いておきたい。
[ad#ad_inside]書き手としての自分はこうだった
書き手としての自分の原点は、小学校2年生頃から書き始めた「お話」にある。学校の「自主課題」としてやっていたのもほとんどこのお話書きで、母親が保存しておいてくれたものだけで、膨大な量になっている。そして、中学高校になっても、寝る前の30分ほど、ベッドでノートに何か書いてから寝るのが僕の習慣になっていた。
ここで大事なのは、この時の僕はほとんど純粋に自分の楽しみのためだけに書いていたことだ。小学校の頃の文章は「自主課題」の一環だったので先生に提出してコメントも時々もらっていたが、それが嬉しくて書き続けたという記憶はない。また、中学に入ってから書いていたのは、誰にも見せることのない、完全にプライベートな、好きな作品のパクリばかりの自己満足の文章だった。僕は今でも、学校の国語の授業ではなく、個人的に読んだ本の量と、このプライベートで楽しく書いた文章が、自分の読み書きの力の源泉だった、と確信を持って言える。「好きな本を読み、書きたいことを書く」ライティング&リーディング・ワークショップに僕が親近感を覚えるのは、この原体験も大きいはずだ。
では、教え手としての自分は…
一般に、学校で書く文章は、(1)人に見せることを前提にして、(2)自分のオリジナリティを出して、(3)構成をあらかじめ考えたり、推敲をしたりして書く。これは、僕の子供時代の(1)誰にも見せずに(2)好きな作品から色々とパクって、(4)準備も書き直しもせずに書く書き方の正反対だ。
また、教え手としての自分も、面白いことに、必ずしも「過去の自分」の道をなぞっているわけではない。それには様々な理由がある。例えば、アトウェルもそうしているように、作家ノートを使って構成をメモ書きしたり、推敲して表現を磨いたりすることが、書く力の向上につながることは、僕にも確信がある。授業の中で力をつけることを意識すれば、「準備も書き直しもせずにただ書く」よりも、明らかに力がつく。
しかし一方で、教師が「力をつける」ことを意識すればするほど、子どもはその教師の「評価」的視線を強く意識する。その視線を内面化して他者の作品と自分の作品の「出来栄え」を比較するようになる。その結果、劣等感をおぼえた子は、自分の書いたものに満足がゆかなくなり、書くことが苦痛になる。そうなったら、書く力がつく道は、ほとんど閉ざされてしまう。かくして、教師が子どもたちの書く力を伸ばそうとすればするほど、力がつかない子が生み出される。(まあ、これはややオーバーな書き方をしてますが…)
2つの自分にどう橋を架けるか?
子どもの頃の経験なんて、しょせんN=1にすぎない。また、自分の子供時代の経験を絶対視するのはプロの仕事ではない。でも、「教師が子どもの力をつけようとすればするほど、力がつかない子が生まれる」危険性を考えたときに、自分の子ども時代の(1)誰にも見せずに(≒匿名性を保ち)、(2)好きな作品から色々とパクって、(4)準備も書き直しもせずに書く書き方に、このパラドックスを解くヒントがあるように感じてしまうのだ。好きな物語に出会って、「こんなもの書きたい!」から出発して、結果としての出来栄えよりも書く事自体の楽しさに書き手の意識が向かうような書き方に。
以前は、こういう書き方は小学校の低い年齢の頃に特有のものだと思っていた(下記エントリ参照)。
でも、決してそんなことはないのだろう。むしろ、書かれた文章の質=「結果」にばかり子どもの意識が行きがちな、さらにカリキュラムもそうなりがちな、中学校や高校の作文指導でこそ、自分の子ども時代のような要素を意識的に取り入れる必要があるのかもしれない。
子どもの頃の書き手としての自分と、いま文章の書き方を教えている教師としての自分。今だって、この2つの自分が離れているわけではなく、無意識に書き手としてのが教え手としての自分に影響を与えているところはあるはずだ。けれど、この2つの自分の間に、もっと意識的に橋を架けること。そこに、僕がこれから進んでゆく道のヒントもあるように思う。[ad#ad_inside]










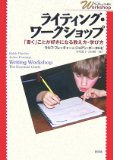

![[資料紹介] 長時間の読書は学力に結びつかない!? 読書活動と学力・学習状況調査の関係に関する調査研究(2009)](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/10/スクリーンショット-2017-10-28-18.19.54-50x50.png)
