細川英雄『自分の〈ことば〉をつくる』を、タイトルに興味を惹かれて手にとり、とても面白く読んだ。「あなたにしか語れないこと」をどう見つけて、表現に育て、それを他者に届けるか。「書く・表現する」プロセスにおける自己と他者の関係を、「対話」を軸にして丁寧に論じた表現論である。
[ad#ad_inside]自分の「好き」から、他者に開かれた表現へ
この本で筆者が論じるのは、自分にしか語れないことを語る言葉、つまり「自分の〈ことば〉」を見つけ、それを書くための方法だ。そして、冒頭4ページの
自分の〈ことば〉を発見することは、それぞれの社会での相手とのやりとりの中で、表現すべき内容と自分との関係にしっかり向き合うことです。
という文章からもわかるように、自分の〈ことば〉をつくるうえで、他者とのやりとり(インタラクション)が欠かせないとする。この相互関係性、つまり「対話」を軸に置くのが、筆者の表現論の特徴だと言えるだろう。
本書で筆者の唱える表現プロセスは次のような順番をたどる。まず、自分の「好き」という感覚・感情に含まれているオリジナリティの核を発見する。次に、それを他者と交換可能な問題意識やテーマにまで育て、自分の考えを持つ。さらにそれを、表現として外化する。外化は、自己の内側にある考えを外に置き、客観視することでもある。そして、この外化された表現に他者が反応し、書き手の思考や表現がさらに磨かれ、充実していく。
書くことにおける「自己」と「他者」の関係をときほぐす
こうした筆者の表現論は、表現における「自己」と「他者」の関係を丁寧にたどっていて、非常に興味深い。副題には「あなたにしか駆られないことを表現する技術」とあるが、本書の核は技術論というよりも書くことの本質論である。また、この本には合計で9つのコラムがあるのだが、それがまたいちいち興味深く、筆者と「対話」をしたくなる。
- 思ったことを感じたまま表現していい
- 「りんごが好き」は自分のテーマになるか
- バイオグラフィとは何か ー語るための中身
- 「内容」か「形式」か
- 情報あっての「私」、「私」あっての情報
- 「正しさ」という幻想
- エッセイとレポートはどう違う ー他者を意識した表現活動へ
- 言語、言葉、ことば ー世界中にあることばとは何か
- モノローグ(独り言)からダイアローグ(対話)へ
この9つのコラム、短いながらも考える点が多いので、書くことに興味のある人はぜひ読んでほしい。
書くことの前提には必ず「他者」がある?
さて、本書で示された著者の考え方はとても面白く、勉強になるのだが、僕の中には少しの違和感もある。それは、筆者があまりにも伝える相手である「他者」の存在を表現の前提におきすぎている(ように見える)ことだ。もちろん、そもそも言葉はコミュニケーションの手段なので他者を前提とする本質を持っている。また、他者に開かれることで自己の考え方や表現も磨かれていく。それは間違いない。それでも僕には、「他者に開かれない」中にも、書くことの大事な側面があるように思われるのだ。
例えば、筆者はコラム「『りんごが好き』は自分のテーマになるか」において、
自分の中では「りんごが好き」という、何らかの思いや感覚があったとしても、それを他者に提示する必然性がない場合、「りんごが好き」は、自分のテーマにはなりにくいものです。(p62)
と語り、テーマとするからには相手へのメッセージ性が必要であると語る。この筆者の論を認めた上で、僕は直感的に違和感も持つ。僕は、率直に言って「りんごが好き」はそれだけで書くテーマになるのではないか、と考えるのだ。
そう思う理由の一つは、僕にとっての「書くこと」の原点の一つが、ノートにひたすら書き続けた僕自身の子供時代にあるからだろう。僕は小学校の時から中学・高校のある時期に至るまで、寝る前にノートにものを書いてから寝る習慣があった。内容は小中学生時代は物語が多く、高校になると競馬の予想であったり馬の話だったりして、要するに雑文だったのだけど、あれが僕自身のライティング経験の原点であることに間違いない。そして、その文章を読む人は僕以外にいなかった。要するに「りんごが好き」をひたすらノートに書いていたのである。それでも十分に楽しく、僕はそれによって書く力を育てた。
書くことは、もちろん他者に開かれている。しかし、他者を前提としない書くこともある。誰にも見せずに、ただ自分のためだけに書く。誰にも見せず、誰からの評価も気にせずに、書くこと自体の楽しみに埋没するような書くこと。それもまた、書くことの本質の一つだということを、僕は経験的に感じている。
僕と筆者のこの違いは何だろうか、と思った。もしかすると、大学生を相手に論文やレポートの書き方を教えてきた筆者と、いまは小学生を相手に教えている僕の立場の違いかもしれない。そうではなく、もっと根本的なものの違いかもしれない。それは今の自分にはよくわかっていない。
ちなみに話題がそれるが、このような「自分のために書く」営みは、学校にいると取り扱いにくい。学校が社会化の装置である以上、授業ではコミュニケーション手段としての書くことにフォーカスを当てざるを得ない。また、評価者としての教師が教室にいる以上、子どもが書く文章は他者の視線にさらされることを強いられる。必然的に、「誰にも見せずに、個人の楽しみのために書く」営みは、学校では無視されてしまう。それは、学校の役割を考えたら仕方ないことでもある。
しかし、そうだとしても、子どもの頃の僕が、いまの教師としての僕を見たらどう思うのだろう。一方では子どもの書く力をつけようとしつつ、同時にそれが子どもの「個人の楽しみとして書く」を侵害していないか。それが気になってしまう。
筆者と対話したくなる本
話を本題に戻すと、僕は筆者の意見に完全に同意するわけではない。でも、この自分のひかえめな不同意は、筆者の意見があってはじめて引き起こされたものだ。これは、筆者が強調する「書くことの相互関係性」の構造そのものである。また、「自己」と「他者」の関係について、筆者が丁寧に取り扱っていることもわかるので、教えられることはとても多い。「書くこと・表現すること」に興味のある人には、ぜひ読んでほしい一冊だ。僕は、読んでとても良かった!
なお、著者は前著の『対話をデザインする』が有名だけど、僕は現時点では読んでいない。これから読んでみたいと思う。
[ad#ad_inside]
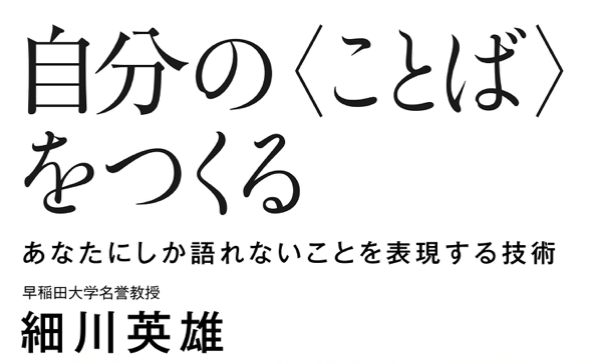




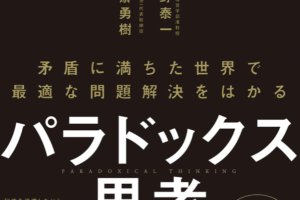

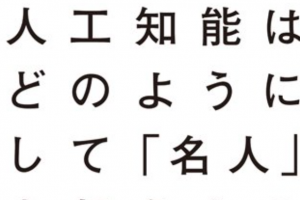
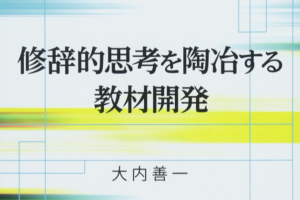

![[お知らせ]公開講座「詩の書き方は教えられるか」の関連動画、「学校・教室で詩の書き方を教えるということ」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2020/10/ca1a45acbf4da0572c47b9b945c8bc84-50x50.jpeg)
