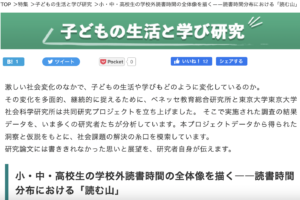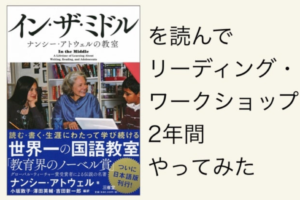GW前に、黒瀬直美さん(@reikosikibu)のオンライン勉強会で、リーディング・ワークショップ(読書家の時間)についてお話しさせてもらった。また、前後して吉田峻さん(@yoyoyoshidaaa)のnote「『イン・ザ・ミドル』を読んでリーディング・ワークショップを2年間やってみた」を読んだ。さらに、今はちょうど今年受け持ちの5・6年でこの授業を始めたところでもある。こうした機会が重なったので、2021年の時点でリーディング・ワークショップについて考えることを書いてみようと思う。ただ、リーディング・ワークショップとはそもそも…みたいなことは書かないので、それは『イン・ザ・ミドル』などを参考にしてほしい。
「自由な読書」ではなく「読む力を高める授業」
まず、先述の黒瀬さんの勉強会でも言ったのだけど、リーディング・ワークショップは「自由な読書」ではない。国語の授業の一環として、児童生徒の読む力を伸ばすためにデザインされた授業の一形態である。だから、それは趣味としての読書とは異なるし、教師による強制も働く。こと読書というと「人生を豊かに」とか「一生の財産」とかウェットな方向に流れる言説が歓迎されがちなのだけど、そして僕も読書大好きな子だったのでそういう言説が嫌いではないのだけど、それでもリーディング・ワークショップを語るときには、あくまで「読む力を伸ばす国語の授業の一形態」であることを強調する方が誠実だと、個人的には考えている。というのも、人生を豊かにするものは読書以外にも無数にあり、「読書は人生の宝物」論では、それらの中から読書だけを特権的に扱う根拠が語れないからだ。
とりわけ日本では、「読解」と「読書」を区別して「読解」を学校で扱い、「読書」を私的な個人の楽しみとして扱ってきた歴史がある(下記エントリ参照)。
だから、「読書=私的な楽しみ」と考える人であればあるほど、その私的な楽しみを、公的な、しかも教員という評価者の目に晒すリーディング・ワークショップに対して嫌悪感を持つ可能性は高い。僕ももともと「私的な趣味としての読書」を楽しんできた子供だったので、そう感じる子の気持ちがわからないでもない。でも、それは変に寄り添うのではなく、甘んじて受けた上で、やっぱり「やりさない」と諭す批判だと思う。通常の国語の授業だって、特定の文章を教材として強制的に読ませてきたのである。その単位が「短い文章」から「一冊の本」になったからと言って、強制性が高まるわけでもない。
リーディング・ワークショップの強み
授業形態としてのリーディング・ワークショップの強みは、「その子の語彙レベルや興味関心に応じたレベルの文章から読める」ことと、「量をたくさん読める」ことの2点である。この2点において、教科書を読み進めるだけの授業は絶対にリーディング・ワークショップにかなわない。読む力は何よりもまず量なのだ。たくさん読むことで、日常会話では得られない語彙を獲得し、言い回しや表現の仕方を知り、流暢に読むスタミナを獲得する。自分にあった色々な文章を読み慣れることを通じて、読むことへの積極性や自信をつけて、新しく出会う文章でも「まず読んでみる」構えを作る。こういう構えを作ることがいかに大切か。言うまでもない。
リーディング・ワークショップの弱み
逆にリーディング・ワークショップの弱みは、多読を優先するためどうしても精読の意識が弱くなりがちなところだ。特に、子どもの自由に任せれば任せるほど、自分の好きな本をただ読み流すような読書に流れがちである。これは今僕が直面している課題でもあって、今年受け持っている5・6年生には読書好きな子も少なくないのだけど、毎回の授業で読むページ数を記録させると、明らかに読むペースが早い。あらすじだけを追うような読み方になっているか、やさしすぎる本を読んでいるかの可能性が高いな、と考えている。
リーディング・ワークショップの教師の役割
リーディング・ワークショップの教師の大きな役割の一つは、こういう彼らの読書状況をアセスメントし、介入することにある。例えば「平易な本の流し読み」になっているなと思ったら、「丁寧に読む」「色々な視点で読む」技術を教える必要がある。例えば僕の場合、今後のミニレッスンで詩を使って精読の練習をしたり、教科書の文章を使って主人公とは別の視点で読んでみる練習をすることを考えている。また、「読む時間」のカンファランスでは、彼らが読んでいる本に色々な質問をして理解度を確かめ、それに応じて、彼らの読書レベルを引き上げたり、幅を広げたりする本を紹介する必要もある。特に、物語と違ってノンフィクションは、放っておくとなかなか生徒は出会わない。「ノンフィクション月間」を設けてノンフィクションの出会いの期間も作るし、カンファランスでも紹介していく。また、ライティング・ワークショップを同時に行うことで、読みと書きを連動させる効果も大きい。彼らは一つ一つの表現を自分が吟味して書く体験を通じて、読む目を養うのである。
リーディング・ワークショップがただの「自由読書」にならずに、一人一人に応じて読む力を引き上げる授業として機能するには、こうした対応が不可欠だ。とりわけ、一対一のカンファランスの影響は大きく、ナンシー・アトウェルの凄みは、なんと言ってもこのカンファランスなのだ。
こうしたカンファランスをするためには、まず教師は読まねばならない。あえて「ねばならない」と書くことでハードルを高くする懸念も感じつつ、心からそう思う。現実的に100パーセントは無理でも、一歩ずつ、そこに向かって前進していきたい。
読書を「さんま」で考えるアプローチ
…と、読者の中には、ここまでですでに息苦しさを感じる方もいるはずだ。原理的に子供が読んでいる本を全て読むのは無理な話だから。そういう方にお勧めなのは、リーディング・ワークショップの実践者でもあり風越の校長でもある岩瀬さんが言っていた、読書を「さんま」で考えるアプローチである。「さんま」とは「時間・空間・仲間」の3つのこと。つまり、読書する時間をどう確保し、読書に適した空間をどうデザインし、読書する仲間をどう作っていくか。この3つの環境デザインで子どもの読書を促していくというアプローチだ。
もともと読書する文化を作る上では「教師−生徒」という縦の関係だけでは不十分で、子ども同士の関係を作ることが不可欠だ。子ども同士の本のお勧めの方が、大人がお勧めするよりも圧倒的に影響力があるからである。僕もリーディング・ワークショップの最初に本の紹介をしてもらったり、最後に今読んでいる本でサイコロトークをしてもらったりを、早速はじめている。これからは、お互いの読みを交流するブッククラブをするのもいいなと思う。
もちろん、そこに大人の側のデザインが何もないと、「5分後シリーズばかりおすすめし合う教室」になりかねない(5分後シリーズに罪はないけど、読む力を伸ばす上で適するとは考えていないので例に挙げた)。だから、アセスメントの視点は必要だけど、それでも子ども同士のお勧めの力を最大限に使って、子供達の読書レベルを上げることはできる。
それでも教師は本を読むべき…と思う理由
実際のところ、教師が本を読まなくてもリーディング・ワークショップを運営することは、形だけなら可能である。アメリカでもそういう(誇らしげな)実践報告を聞いた。
ただ、それでも僕は教師は本を読むべきで、しかも、その子達が「いま、ここで」読んでいる本を読むのが大切だと考えている。その子がいま楽しく読んでいる本を知らないで、その子の現在地を知ることなどできない。また、それ以上に、その子の好きな本に共感できない大人が本を勧めたところで、読んでもらえるはずなんてないからである。
自分が知らない本のカンファランスをするときは、どうしても表面的に理解度をチェックするような質問になってしまう。本の中身に入りきれない。でも、その本の内容を知っていればこそ、本の前の同じ読者同士として、「このところ良かったよねー」「自分はここが好き」という話ができる。教師と生徒が対等ではない以上、こういう会話は「擬態」の側面もあるのだけど、たとえそうだとしても、こういう「擬態」は重要だし、楽しいものだ。
読書生活はガラリと変わります
というわけで、この4月から5・6年生を持つことになって、僕は2日に1冊以上のペースで児童書を読んでいる。子どもたちに本を勧めてもらうようにお願いし、勧めてくれた本は必ず読む(そういうやりとりをした子は、こっちのお勧めする、ちょっとハードルの高い本や読む幅を広げるための本を手にしてくれる可能性が高い)。他に読むときは、こちらが紹介しないと出会いにくい名作系やノンフィクション、人気のあるシリーズ物の少なくとも一つを読む。「〇〇さんに良さそうかな」と、お勧めする相手を想定して読むことも多い。リーディング・ワークショップをすると、どうしてもこういう読書生活になるので、なかなか大人向けの本を読めなくなってしまうのが、悩みといえば悩みだ。これもまたなかなか楽しいけど、高校で現代文を教えていた頃とはもう読書傾向が完全に変わっちゃったなー。
今年の受け持ちの子には、もちろん読書が苦手な子もいる。逆に、もう7・8年生と比べても遜色ないレベルの本を読んでる子もいる。どの子にも、より多くの読書を通じて、読む力をつけてもらうのが僕の仕事の一つ。「豊かな読書」だって、当然その道の先にあるに違いない。というわけで、とにかく今年度は児童書を読んでいきます!
[ad#ad_inside]