先日、横浜で小学校の先生が主宰している読書会「大人のブッククラブ」に参加してきた。今回の課題本として読んだのがリヒテルズ直子さんと苫野一徳さんの共著『公教育をイチから考えよう』。読書会の感想を織り交ぜながら、感想を簡単に書いてみたい。
「そりゃあわかるけどさあ!」
読書会って面白いなと思うのは、自分にない観点の感想が参加者から出てくるとき。今回は第1章のリヒテルズ直子さんの日本批判のところにけっこう怒っている方(小学校の先生)と、それに同調する方(中学校の先生)がいた。「そりゃあわかるけどさあ!オランダは羨ましいけど、日本の風土で頑張ってるのに!」な感じだったようだ。僕はそこは全然気にならなかったので、この怒りや違和感の表明はとても新鮮だった。
読み直してみると、確かに日本の教育のマイナス面がやや誇張して描かれていると思えるし、逆に良いところにはあまり触れられていない。僕自身はイギリスで一年間暮らした結果「日本の小学校はすごいなあ」と感心したところも多々あるだけに(下記リンク)、このリヒテルズさんの書きぶりは額面通りは受け取らないけど、言われてみるとちょっと煽り気味なのかなという気はする。
二項対立で読まれてしまう?
そして、このオープニングのせいで、全体としてこの本の内容が、ちょっと歪んで受け止められるのではないかという気もした。
この本、お二人の立ち位置として、リヒテルズさんがオランダと対比する形で日本の教育の問題点や課題を指摘し、苫野さんはそのリヒテルズさんの問題提起を受け継ぎつつ、今後の教育のあるべき姿として、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合」について提案するという構造になっている。
で、この構造で、加えてあのオープニングだと、どうしても読者が一連の議論を二項対立的に捉えやすくなるんじゃないかと思う。つまり「今の日本の教育は問題だ」「だからオランダに倣って、学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合をすべき」というように。実際にはそんな単純化された主張はなされていないのだけど、どうしてもそういう印象を受ける。
これ、ちょっとこの本のもったいないところじゃないかなあ。僕自身、この印象に引きずられて、読書会で「でもアジア型の教育って粘り強く学ぶ人を生むのかも」と言ってしまったのだけど、そういう「日本対オランダ」的な二項対立に話を落としてしまうと、見えるものも見えなくなるなと後から反省した。
この本の面白いところ
リヒテルズさんが書いているオランダの教育の話は、個々のエピソードとしては面白い。もちろん全体としてオランダの教育に肯定的な話が多く、特に、1960年代以降のオランダの教育改革の話には、こんな大胆な転換が実際にできるんだなという驚きとともに、勇気づけられる。一方で、シチズンシップ教育の課題(p.97)など、「オランダでもそうなのか」と思わされる課題の指摘は、教育現場のリアルを感じさせた。あとオランダの小学校の哲学授業で使われているらしい50枚のカード教材、あれ欲しい(p.160)。こんな問いなんですよ。
人は泥棒でも愛してしまえるのか どのドアも開けられない鍵は鍵と言えるのか 誰か他人の未来を盗むことはできるか 白鳥は自分が美しいことを知っているか
また、苫野さんの一連の議論は、僕はすでに『教育の力』を読んで、そこの考え方を受け入れているので、そう目新しいことはない。
しかし、読んでいて、現在の教育の動向も踏まえて、より実践に寄ってきたなという印象がある。「一斉アクティブ・ラーニング」(p215)とか、苫野さんのネーミングセンスは素晴らしい。現場にいる僕らに届く言葉を使う方である。
共著になっている効果は?
お二人の仕事はそれぞれに価値のあるものだと思うだけに、1+1=3になっていないという意味で、全体としてはちょっともったいない本なのかも?と感じた。対談も、対談ならではの新しい知見があるというよりは、お二人が個別にも言いそうなことを承認しあっている印象。全体としては、個別の単著ではなく、わざわざ共著になっている意味が、個人的にはあまり感じられなかったかもしれない(むしろ、構成のせいで先に書いたような事態を招く可能性もあると思った)。まあ、僕はお二人の仕事をきちんと追っかけているわけではないので、一時的な印象かもしれませんが。
とはいえ、かなりとっつきやすい本なので、例えば『教育の力』を読む前にこの本から手に取る、というのはアリな選択肢だ。各種SNSを読む限りこの本を肯定的に読んでいる教員の方も多いようだし、ぜひ手に取ってみてください。





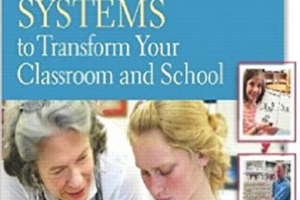



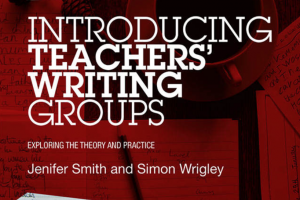
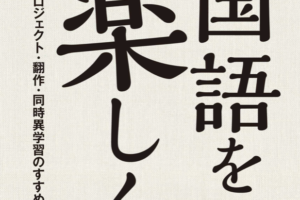


![[宣伝]8/2(土)、木村彰宏さんを講師に迎えて、コーチングを教育に活かす研修を実施します。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2025/07/94c3cf9763ea69d0a146bdcd638a4b02-50x50.png)

![[読書]基本的情報から実践者たちの「いま」まで、リーディング・ワークショップの魅力を伝える決定版。プロジェクト・ワークショップ『改訂版 読書家の時間』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2022/07/12c4c9c6f0a7ef5cc195154935992b5e-50x50.png)