『公教育をイチから考えよう』の読書会(下記エントリ)の流れで手に取った苫野一徳さんの『どのような教育が「よい」教育か』。この本こそ、公教育をイチから、いやゼロから考えている本だった。とても好きな本なので強力にオススメする次第。
このレビューが長いのであらかじめ簡単にまとめると、
- 人間の本質から教育の本質を解き明かす
- 正当化される教育の原理を解き明かす
- 教育関係者、特に教育行政に関わる人向け
の本だと思う。
[ad#ad_inside]人間の欲望から教育の本質を導く
この本はタイトル通り、苫野さんが「よい教育」の本質について徹底的に考えた本である。『教育の力』や『公教育をイチから考えよう』を読んだ方にとっては、そのお話の土台になる部分だと思っていただければよい。
この本の構成
この本は、次のような構成になっている。まず「良い教育とはどのような教育か」という問いの立て方をする教育論の多くが悪しき相対主義に陥ってしまうという限界を踏まえて(第1章)、そのアプローチの代わりに「私たちはどのような教育を欲するか」という欲望論的アプローチをとることを正当化する(第2章)。その上で、欲望論的アプローチに基づいて、望ましい社会のあり方をもとに教育の根底にある原理を提出する(第3章)。そして、この原理のもとで様々な教育論を「対立する諸原理」ではなく、「同一原理のもとでの相互補完的な実践理論」へと読み替え、望ましい教師像や教育行政のあり方について提言するのだ(第4章)。
読んでいてとてもスリリング!
こう書くと手短かすぎて何のことだかわからないと思うのだけど(すみません…)、特に面白かったのは、欲望論的アプローチがその他の複数のアプローチ(道徳・義務論的アプローチ、状態・事実論的なアプローチ、プラグマティックなアプローチ)に比べて優位にあることを示した第2章。そして、欲望論的アプローチに基づいて、人間が<自由>になろうとする欲望を持つ存在であることから、社会の構想原理を<自由の相互承認>に置き、そこからさらに教育の本質を、
教育の本質=各人の<自由>および社会における<自由の相互承認>の<教養=力能>を通した実質化
だと導いていく第3章。この辺りは、読んでいてとてもスリリング。個人と社会と教育が一本の線で繋がっていく感じだ。
教育の正当性の基準は、「すべての人の自由の実質化」
上のような議論の手続きを経て教育の原理を明らかにしたのち、苫野さんは、具体的な「教養=力能」の内容に踏み込んでいく。義務教育段階では、それは
- 諸基礎知識
- 学び(探究)の方法
- 相互承認の感度
なのだという。苫野さんによれば、ある教育が正当かどうかは、こうした力能をすべての人に身につけさせ、すべての人の自由の実質化を促進しているかどうか(一般福祉の原理)を基準にして評価されるのである。
ここで大切なのは、具体的にどんな教育が良いか悪いかが、あらかじめ決まっているわけではないということだ。あらゆる教育は、この一般福祉の原理に照らし合わせ、その場の状況や問題関心に応じて判断される。状況への関心を抜きにして「いつでもどこでも正しい教育」というものは存在しない。経験主義の教育が良いとか詰め込み主義が良いとか、そういうことは言えない。全ての教育政策・教育方法は、教育の原理に照らし合わせつつ、それがその状況下で有効な実践理論として機能するかどうかで判断されるのである。
したがって、一見すると生徒の「自由」を拡大するような政策も、それだけでは支持されない。実際に苫野さんは、教育の原理と現代日本の状況を照らし合わせて(彼の用語でいうと「目的・状況相関的に考えて」)、次のように述べている。
この観点からすれば、私は少なくとも今後しばらくは、学校の民営化もホームスクーリングも、現代日本の公教育の主流にはなり得ないだろうし、またなるべきではないと考えている。少なくとも今の段階では、それは一部の意識の高い、あるいは経済的に恵まれた人々の<自由>を集中的に促進することにはなりうるが、そうでない人々の<自由>については、著しく阻害することになるからだ。(p147-148)
「自由な学校」よりも「自由への学校」を
さて、これ以降は、この本を読んで思ったことを2点記したい。一つは、いわゆる「自由な校風の学校」について(僕の勤務校もそういう学校の一つである)。もう一つは、『教育の力』以降に苫野さんが唱えている「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の“融合”」とこの本の関わりについて、である。
「自由な学校」は理想の姿なのか?
東京には偏差値上位の私立校を中心に、「自由な校風」と言われる学校がある。こういう学校は、多くを生徒の自主性に委ねているぶん、苫野さんの言う教育の本質的あり方に近いのだろうか?
おそらく、そう単純にイエスとは言えないだろう。自由な校風の学校は、たしかに生徒の主体的な意思決定に任されている部分が大きい分、生徒が自由を行使する感覚が磨かれやすい環境ではある。しかし、だからと言って「自由な学校」が即「良い学校」なわけではない。というのも、「自由な学校」は、ともすれば「もともと高い力能を持っている者=<自由>な者が、与えられたチャンスを生かして、より力能を高めていく場」に、容易に転化しうるからだ。
従って「自由な学校」でこそ、<自由の相互承認>への感度をお互いに高めることが大事になってくる。それがない「自由な学校」の自由は、ただの「強者の自由」であり、一般福祉の原理に反するので、正当化されない。つまり、本当に求められるのは、「自由な学校」ではなく「自由への学校」なのだ。
個別化・協同化・プロジェクト化は「ゴール」ではない
また、このような「自由への学校」の教育プログラムとして、苫野さんが近年唱えているのが「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の“融合”」である。『教育の力』(2014)と『公教育をイチから考えよう』(2016)では中心をなしているこうした提案は、こちらの『どのような教育が「よい」教育か』(2011)ではまだ触れられていない。
しかし、この本を踏まえた時、なぜ「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の“融合”」という提案が出てきたのかということがよくわかる。そして、これが、あくまで各人の自由および自由への相互承認の感度を高めるための実践理論であり、ゴールそのものではないこともよくわかる。ベースになるのはあくまでこの本に書かれている理論であり、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の“融合”」は、現代日本の文脈において教育の原理を現実化するための「実践の方法」に過ぎないのだ。究極のところ、手段であって目的ではない。
個別化・協同化・プロジェクト化は、一斉授業と対立しない
こういう風に見ると、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の“融合”」が、「知識の暗記」「系統学習」「一斉授業」というキーワード群と対立するものでないこともよくわかる。この本の立場を尊重する限り、どんな学習方法であれ、それがすべての生徒の<自由>や<自由の相互承認の感度>を高める方向を向いて有効に機能している限り、正当化されうる。
現代日本においては「個別化・協同化・プロジェクト化の“融合”」が目指しうる具体的な姿であるというのは事実だろう。でも、目標が共有されている限り、これらは一斉授業と対立するのではなく、相互補完的でありうる。こういう認識は、二項対立を固定化させないという意味で、とても大事だと思う。この原理の部分をしっかり持っている限り、どんな現場でもおそらくできることがある。
特に教育行政に関わる方に読んでほしい…
苫野一徳さんの著作を、『どのような教育が「よい」教育か』(2011)、『教育の力』(2014)、『公教育をイチから考えよう』(2016)と順番に進んでいくと、彼が理論から実践へと徐々に軸足を移していることがよくわかる。その意味で、後半に行けば行くほど現場の教員にとって読みやすくなっている。
でもどれか一冊をあげるとしたら、押さえておくべきなのはこの本だと思う。少なくとも僕にとってはベスト。ここの根っこを押さえておけば、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の“融合”」を金科玉条のように扱う誤解を避けることもできるし、自分の現場に応じて自分がなすべきことを判断できる。そのメリットは大きい。
そんなわけで教育関係者の方にはおすすめしたい本だが、中でも特に、教育行政の方にはぜひ読んでもらいたい。教育のおおもとの方針を決め、莫大な予算の権限を持つ立場の人にこそ、こういう「ゼロから考える」ことが必要だと思うからだ。
あと、個人的には、苫野さん以外の教育哲学の本ももっと読んでみたいと思った。これを読むと苫野さんの議論に納得してしまうのだが、別の本を読むとそうでなくなる、ということもあるのだろうか。ぜひそういう体験をしてみたい。昔手にとったデューイをまた読むのもいいけど、正反対の議論も読んでみたいな。誰かお薦めを教えてください。
[ad#ad_inside]
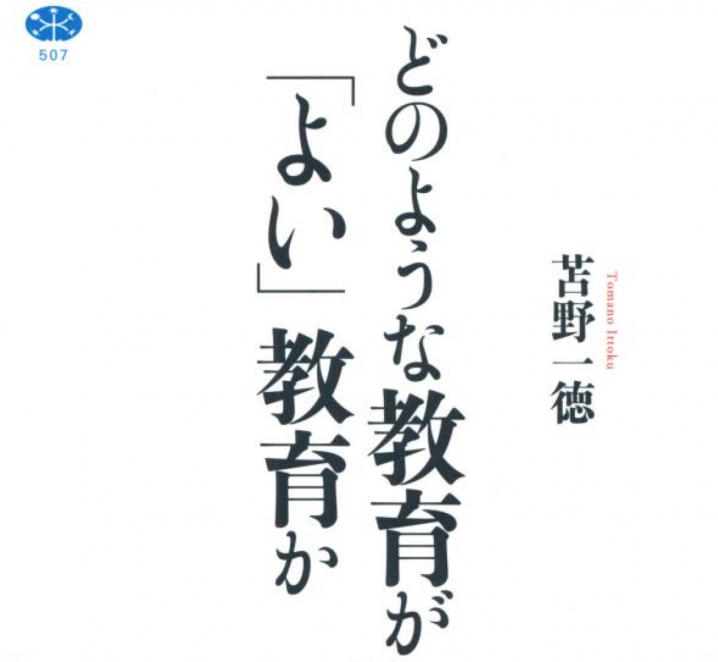



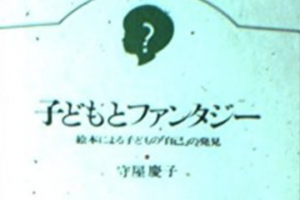








進歩主義的な教育のカウンターとして登場したのが、ブルーナーの『教育の過程』だったと思います。一回読んだだけで、あやしげな記憶です…。系統性を大事にする考え(古くは、プラトンもそうみたいです。)だったと思います。
最近読んだのでは、デューイと反対ではないですが、デューイの教育学を批判するもので、キエランイーガンが素晴らしかったです。デューイ教育学の価値がなくなることはないと思いますが、デューイやブルーナーなどの教育学を補完、統合するものとして優れた教育体系を書いていると思います。いくつか本がありますが、イーガンの思想や理論を体系的に最も詳しく扱っているものとして『想像力と教育: 認知的道具が培う柔軟な精神』が一番いいと思います。実践に重きをおいた本もあります。
プラトンなどの系統的な教育理論、デューイなどの経験、直観、体験を大事にする教育理論、あと個性化、この三つが教育思想の三大潮流だとイーガンは指摘していました。その三つを統合するのがイーガンの教育学体系だということで、面白かったです。
岩瀬さんがブログで紹介している「深い学びをつくる」もこのイーガンさんの本ですね?
てるさん、ありがとうございます。勉強します!
そうです。岩瀬先生がブログで紹介してた「深い学びをつくる」のイーガンです。「深い学びをつくる」は、イーガンの発信している教育論で、もっとも有望株みたいです。翻訳されているもので、理論的背景を詳しく知るには、『想像力と教育: 認知的道具が培う柔軟な精神』が最も優れていると思います。
あすこまさんが、前に迷っていたときにプッシュしてくれた『ヴィゴツキー入門』柴田義松を昨日から再読しています。
「子ども時代の教育は、発達を先回りし、自分の後ろに発達を従える教育のみが正しい」(『思考と言語)』)
発達の最近接領域から教師の主導的な役割を主張ところなど、ヴィゴツキーは、児童中心的な教育論の反対の視点を提供してくれているのかなと思いました。
でも、この入門書の『教育心理学講義』を解説したところをよく読むとデューイと重なる部分があったり(子ども個人の経験を重視するところ)、デューイのフォロワーは、おそらくデューイを誤解していたのだろうと思うところがあったり(入門本のはじめのほうに出てくるソビエトのコンプレックスシステムの人たち。デューイは単純な子ども中心主義ではないから)、面白いです。イーガンを読んでから、『ヴィゴツキー入門』に戻ったら新しい発見がありました。
連続コメントすみません。教育哲学ということで思い出してしまいました!
教育哲学と言えば、
牧口常三郎の『創価教育学体系』もおすすめです。
ヘーゲルから原理を取り出す苫野さんの教育論にも納得ですが、僕はその教育哲学がすべてではないと思っています。教育学理論や教育実践の原理となる有力な教育哲学という意味で、『創価教育学体系』をおすすめしたいです。『創価教育学体系』は、カントやマッハの哲学を教育の分野に応用しているみたいです。『創価教育学体系』も西欧哲学の地続きにあります。
イーガンは、プラトンの教育理論(哲学)から振り返って、教育論を展開していて、この人も、そもそも教育とは何かというレベルから一つの教育哲学を展開しているように思います。イーガンからは、苫野さんとも牧口常三郎とも違う視点をもらいました。
牧口常三郎の教育哲学を研究した思想史の本として斎藤正二の『牧口常三郎の思想』もおすすめしたいです。スリリングで、めっちゃ面白いです。