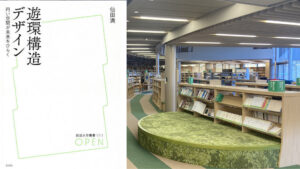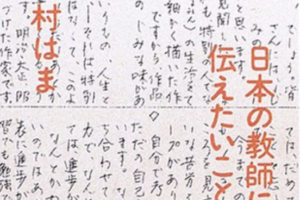安斎勇樹・舘野泰一『パラドックス思考』を読んだ。「あれかこれか」の二者択一が溢れる中で、一見矛盾した「Aもしたいけど、その反対のBも必要だ」というパラドキシカルな感情をどう飼い慣らし、二者択一に陥らないかをテーマにした、とても面白い本だった。読んでいると、どうしても具体的状況を自分に引きつけて読んでしまう。そんなわけでこのエントリも、本書のレビューというよりは、本書を手がかりに自分が振り返ったことや考えたことが中心になる。
[ad#ad_inside]世界は「無理ゲー」で溢れている
「仕事も思い切りやりたいが、家庭も大事にしたい」「部下のやりたいことも尊重したいが、それだと自分のやりたいことができない」….僕たちの日々の生活には矛盾した感情がいっぱいだ。これを両方とも整合的に満たすのは「無理ゲー」だし、どちらかを取ればどちらかが満たされない。僕たちの生きる世界は、こんな「無理ゲー」で溢れている。
筆者たちはこうした感情の矛盾を「感情パラドックス」と名づけて、それをどう取り扱うべきかの処方箋を提示する。面白いのはいきなり「処方箋」にいく前に、そもそもこうした感情パラドックスがなぜ生まれるのか、人間の感情や心理の問題(第2章)や社会構造の問題(第3章)にまで踏み込んで分析していることだ。ここを読むと、僕たち人間がそもそも「めんどうくさいけれど愛らしい、矛盾に満ちた存在」(p50)であることがよくわかる。この人間観は本当に大事にしたいところ。僕の場合は自分の開き直りに使っちゃうのがよくないところだけど…。
こうした洞察の上に立ち、筆者はこの感情パラドックスの基本パターンを整理して(第4章)、次の3つの観点からその受容法・活用法を提案する(第5〜7章)。
- パラドックスを受容して、悩みを緩和する
- パラドックスを編集して、問題の解決策を見つける
- パラドックスを利用して、創造性を最大限に高める
とまあ、こんな感じの本なのだけど、自分に引きつけて読んでみると色々と面白かった。感情パラドックスのない人生なんてないので、誰でも自然と自分に引きつけながら読める本だし、その方が読んでいて面白いと思う。というわけで、純粋な本書の紹介はここまでで、以下は自分に引きつけた文章が始まる。
パラドックスは面白い
僕にはもともと、パラドックスを「悩ましい」というよりは「面白い」と思う傾向があったと思う。それはきっと、僕のかつての専門であった高校の現代文読解において、パラドックス(逆説)が重要なレトリックだったことと無縁ではない。僕の関わった『中高生のための文章読本』でも、「評論と楽しく付き合う4つのコツ」コーナーでも「逆説的発想を楽しむ」コツが挙げられているが、一見すると矛盾する論理の面白さは、レトリックとしてとても魅力的なのだ。矛盾から何か別のものが生まれる面白さを、僕は評論のレトリックを通して教えられた。
風越学園でのパラドキシカルな日々
とはいえ、それは思考遊戯としての面白さであって、仕事の上でパラドキシカルな感情にそんなに自覚的だったわけではない。その後、風越学園に来たことで、僕の「パラドックスにどう向き合うか」という意識が強まってくる。
そもそも、「外野」から見た時の風越学園は、次のような極めて安直な二項対立構図の中で、「理想の学校」的に語られることがある。
| 公立学校 | 風越学園 |
| 画一 | 多様 |
| 強制・制約 | 自由 |
| 一斉授業 | 個別自由進度 |
| 教科 | プロジェクト・探究 |
| 同学年 | 異年齢 |
| スクール形式の教室 | 自由なレイアウト |
| 学ばせたいことから出発 | 子どもの関心から出発 |
| 時間割がある | 時間割がない |
| テストがある | テストがない |
| チャイムがある | チャイムがない |
在校生や保護者ならわかるように、この二項対立構図は現実を正確に反映していないし、仮にこの二項対立構図が正しいとしても、少なくとも僕は別に右側だけが「正しい」とも思っていない。現実は、というより人間はそんなに単純ではないからだ。(以下、便宜的に「子ども」と書いたところは大人も含めた全ての「人間」に当てはまることだと僕は思っている)
例えば、「自由」で「子どもの関心から出発」すれば豊かな世界が生まれるかというと決してそうではない。子どもの興味関心から離れた世界に出会う機会がなければ、いつまで経っても彼らの世界は広がらないし深まらない。それでは、本当の意味での、自分で選択して決める「自由」に近づかない。だから、彼らが自由になるには何らかの強制・制約が必要だ。この一年半程度の僕の授業設計は、この「どんな制約が子どもを自由にするのか?」の追究でもあった。
さらに、テストや数値で競うことがよくないという考え方にも、今の僕は一歩距離を置いている。今年の国語では、毎回の漢字テストの結果や「読書1万ページ」のページ数を国語教室通信で掲載することにした。これはある意味で、とても「風越学園らしくない」要素だが、多くの子どもたちの反応から、僕はこれにも確かな手応えを感じている。
数値による競争・序列化をゼロにすれば良いわけではない。問題なのは「数値だけ」の価値観に染まってしまうことであり、暗記や積み重ねが必要な分野における、そういう外発的動機づけ自体が問題なわけではないのだ。このテストや数値のように、「その学校(ここでは風越)の支配的な文化に矛盾する要素を、日常の中にあえて入れる」ことに、今年の僕はけっこう自覚的だった。それは、一つの方針で論理的に統一できるほど、人間は単純な存在ではないからである。
さらに、以前に下記エントリで書いた風越の「回遊型」環境もまた、僕たちの感情パラドックスをうむ存在である。
開放的で流動的なデザインは、風越を特徴づけるものでもあり、東京学芸大学の渡辺貴裕さん「「いつでもどこでも」とは異なる「今ここ」での経験~アウトプットデイに現地参加して~」のようにアウトプットデイではその真価を発揮するが、一方でその中で集団を相手に日々の授業をするのはかなり大変なのだ。ここにも、デザインに込められた理念を実現したい思いと、一方で最低限の学力は保障してあげたい思いという、感情パラドックスがある。
というわけで、風越学園は全く夢の国ではないし、むしろ先の表の左側にある公立学校の仕組みがいかに安定的で優れているかを、僕は風越に来て一層自覚するようになった。実際、ここで働くスタッフの多くは、表の右側ゆえの「しんどさ」を経験している。それは、渡辺さんも先の記事で次のように書く通りだ。
率直に言って、風越のスタッフは大変だと思う。
決まった制度や慣習が多い一般的な学校では、もちろんそうした制約にフラストレーションを感じることも多いだろうけれど、一方、ある面では教師は、「今の学校の仕組みでは…」「与えられている教科書では…」など何かのせいにして、「逃げる」ことができる。けれども、風越の場合、自由度が高く、その気になればいろいろなことができる(ように思える)ため、そのように何かのせいにして自分を守ることができない。目の前でうまくいかないことが起きたとき、その責任もそこからの脱却も、全部自分の肩にのしかかっているように感じられてしまう。これはしんどい。常に、「足りない」「できていない」感に追われる。
この文章の趣旨はむしろ引用後の部分にあるのだが(だから記事全体を読んでほしい!)、それでもこの指摘は僕が以前に、以下のように書いた状況とも重なる。
経験の浅い若いスタッフは、基本問題に習熟する前にいきなり応用問題を解かされるようなものだ。また、風越にはそれぞれの現場で名を馳せた実績あるスタッフも少なくないが、熟達の腕を持つ彼らでさえ、かつての実践と同じことを風越でやろうとしたら「パワード・スーツ」の助けがないため以前ほどの成果を出せず、「こんなはずではないのに」と不全感を抱くのではないか。風越学園は、ぶっちゃけそういう空間である。
そう、だから決して先ほどの表の「右側」がよくて左側が「悪い」わけではない。左側の学校が持つ制度的な制約によって、子どもも大人も守られていることはたくさんあるのだ。「あれかこれか、どっちがいいか」の二項対立で語れることではない。
教育はそもそも矛盾する営み
こんなふうに、風越で働く日常は、いろいろなパラドックスに直面し、それを意識する日々である。とはいえ、僕はそれを「さて、どうしようか」と楽しんでいる面もあって、決して嫌いではない。そもそも教育とは、「今のままのあなたでいいよ」と「今のままのあなたではいけないよ(あなたはもっと成長しないといけないよ)」を同時に子どもに言うような、矛盾する営みなのだ。風越学園の中に矛盾がたくさんあるということは、風越学園がまっとうに教育に向き合っている証だ、くらいに思っている。
パラドックスの「手なずけかた」
風越の話が長くなったが、では、本書、安斎勇樹・舘野泰一『パラドックス思考』は、「パラドックス」をめぐるこういう僕の関心に、どんな示唆を与えてくれるだろうか。
まず、感情パラドックスが生まれる精神や動機の構造について説明する第2章は、本当に「あるある」すぎて単純に面白い。例えば、「パラドックスを生み出す心の構造」として紹介されるジャック・メジローの「変容的学習の10段階のプロセス」(p78)は、風越に来てからの自分の経過をそのままたどっているようだし、行為そのものに興味がある内発的動機づけと行為の外に動機がある外発的動機づけの関係性(p84, 「やりたい」と「やらねば」の衝突)は、教育現場にいたら誰もがそのバランスに苦慮していることだろう。
また、「飽き」が生み出す、「やってきたことを続けたい」と「飽きたので違うことに挑戦したい」という感情パラドックス(p92)は、僕自身のキャリアを振り返っても納得のいくところだ。僕がなんだかんだで風越で働けているのも、先述したいろいろなパラドックスや新しい挑戦に直面して「飽きていない」ところが大きい。
また、風越での組織の特徴として、通常の学校よりもきちっと組織化されていない点がある。これも開校初年度はそれが「良さ」として語られていたが、働いているとそうでもないことがわかってきた。組織化されていないが故に、「落ちたボールに気づく人が永遠にボールを拾い続けて不満がたまる」構図があったからだ。明確な役割があることの意味は大きい。かといって役割だけやるようだと組織が硬直化する。ここでも、「集団の役割分担と役割外行動のパラドックス」(p112)が存在する。
このように、本書は風越学園で自分が経験したさまざまなことに説明の言葉を与えてくれる。まずはそれが本当にありがたい。こういう言語化があると、何か問題があったときにも、自分と衝突する相手個人を責めずに「学校のパラドキシカルな問題」として、一歩俯瞰して捉えることができるからだ。
また、その処方箋として、第6章の「パラドックスを編集して問題の解決策を見つける」は、「AかBか」のパラドックスを解きほぐす発想のパターンを紹介してくれて、思考の補助線になる。切り替えの条件を設定して作業を切り替える「切り替え戦略」は個人的なワークライフバランス見直しに役立ちそうだが(例えば休日の仕事時間が一定量を超えたら必ず楽器の練習を30分するなど)、個人的に一番魅力を感じるのは、一見対立するAとBの間に因果関係のストーリーを作る「因果戦略」だ。僕はやはり、こういう、現代評論的なレトリックに惹かれる。例えば、風越の校舎デザインの話で言うと、「動き出したくなって偶然の出会いをうむ、開放的で回遊型の校舎」(A)と「一定水準の学力をつけたい思い」(B)を対立項として捉えるのではなく、「この校舎だから学力が(学力も)育つ」ストーリーをどう描いていくか。そこに、僕たち風越スタッフの「物語を作る力」が問われるのだろう。
個人として心がけたいことも挙げておく。一つは、「得意技の罠」(p91, コンピテンシー・トラップ)に気をつけること。僕は比較的、得意と不得意がはっきりしている教員だ。得意なことは成果を上げやすいが、その成功体験に捉われすぎると変化するチャンスを失ってしまう。ここは実際どうするかというと難しいなー。
もう一つは、自分であれ他人であれ、真の願望は言語化されていない場合が多いことを視野に入れて、「反転感情チェック」をすること。健康な人が健康を特に意識しないように、実際には感情パラドックスがあるのに、それが自覚されていない場合は結構多そう。そこのチェックは意識的にしていきたい。
感情パラドックスを飼い慣らすために
やや雑駁に書いてきたが、本書を読んでいるとこんなふうに思い当たることがたくさんある。それだけ、僕らの世界は感情パラドックスに満ちているのだ。この感情パラドックスは人間である以上なくならないし、である以上は悲観することも、まして他人に対して「首尾一貫していない!」と怒る必要もない。飼い慣らしていくしかない。本書はそのための処方箋として、とても面白い一冊だと思う。
[ad#ad_inside]