このお正月休みで何冊かの本を再読した。その中で、「以前に読んだ時も面白かったけど、今の自分にとっていっそう大事な本」がある。それが梅田卓夫・清水良典・服部左右一・松川由博『新作文宣言』だ。現在主流の「文章の書き方本」とはおよそ異なる、1989年刊行の本書は、しかし、作文教育のもっとも大事な点をついている。それは、文章を書く価値は、書かれた「作品」にあるのではなく、書くプロセスにこそあるという点だ。改めて教えられることの多い本書について書いておきたい。
[ad#ad_inside]あの「高ため三部作」の著者による作文論
この本の著者4名の名前に覚えのある方も多いだろう。伝説的なベストセラー『高校生のための文章読本』『同・批評入門』『同・小説』いわゆる「高ため三部作」を世に送り出した4名の高校国語教師(当時)である。僕もかつて高校教師だった時にこの三部作を読んだが、目配りの広さ、選ばれた文章の面白さ、毒やユーモア(おそらく、現代であれば教育的配慮で掲載できない作品も多い)、短いながら的確な解説など、自分には遠く及ばぬ力量に驚き、こんな4名が同じ職場にいるなんて奇跡ではないかと思ったものだ。
自己創造としての書くこと
本書の中で、筆者たちが唱えるのは、自己創造のための作文論だ。「あそびをきらい、つねに真面目な内容を、良いことばで書くことを求める」(p12。ページ数は単行本のもの。以下同)の学校の作文指導は、文体にせよ内容にせよ「こうあるべき」という規範意識に縛られている。しかし、その規範意識に縛られたら、もうそこに「自分」はいない。
もともとは考えていなかったことでも、文章の規範的なスタイルによって、なんとなく結論が導かれていって、やがてその方がカッコいいと思う。のみならず自分はそれを”考えて”いたのだと信じてしまう。こうして知らず知らずに〈規範〉は私たちの思考にも癒着してくる。(p38)
筆者の言う通り、書くときに規範的スタイルを守ると、書き手はまるで自分が考えていたように勘違いしてしまう。しかし、その時、本当は規範的書き方にとらわれているだけで、何も考えていないのではないか。これは、僕がもう20年以上前に当時流行していた樋口式の小論文指導に感じた違和感と同じだ。そこには、「Discovery Writing」ー自分自身が何者かを模索し、発見するプロセスがない。筆者は、そのような作文には価値をおかない。筆者によれば、書くことは「自分」づくりの”現場”(p40)なのである。
作品主義からの転換
では、どうすれば「自己創造としての書くこと」が可能になるのだろうか。筆者たちが力点を置くのが、完成作品よりもそのプロセスに注力することだ。従来の作文教育を、「完成作品にばかり目がいっていて、本当の意味での〈表現の現場〉の指導がなおざりにされてきた」(P166)と批判する筆者たちは、作品主義からの転換を主張する。
いい作品を書こうなどと思わなかったころ、わたしたちの筆はどれだけでもうごいたのではなかったか。こどもたちが何のためらいもなく線を引きはじめるのは、そのためではないだろうか。ことばに自分を押しこめようとしなかったころ、ことばはもっとわたしたちと親密ではなかったか。(p10-11)
〈表現の現場〉はメモにあり
そして、完成作品の代わりに筆者たちが作文教育の主軸に据えるのが、作品創造の現場である「メモ」なのだ。
実践的な作文にあっては、〈表現の現場〉は、まず〈メモ〉にはじまる。文章を書くという作業をトータルにとらえるとき、身体と心が同時にはたらいてその作業にはいるのは〈メモ〉が最初である。わたしたちは、文章を心や精神だけで書くのではない。手が不自由な人でなければ、まず〈手〉が参加して、はじめて文章は〈書かれる〉のだ。(P166)
本書の「メモ」論の独自性は、「作品を創造する準備(手段)としてのメモ」という位置づけをあらため、むしろメモの持つ主観性・未決性・暗示性にこそ、表現の本質を見る点にある。メモと完成作品の立場は逆転し、「〈メモ〉という現象を、人間の言語活動の一つの先鋭なあり方として、あらためてとらえ直してみると、逆に”完成作品”を思考の残骸としてとらえる目も可能になる」(P181)。こうした見方は、たとえば「作家ノート」に対する僕たちの見方も新しくしてくれる。作家ノートは完成作品を書くための手段なのではない。作家ノートにこそ、生の表現があるのだ。
自己を作るプロセスとしての推敲
もう一つ、本書で特徴的なのが推敲の扱い方である。通常、推敲とは「読む側にたって文章を読み直し、手直ししよう」(P210)というプロセスと説明されがちだが、筆者たちは「書く側にたった推敲」という観点から、推敲は作文の執筆プロセスのあらゆる場面でおこっている、と主張する(これと同様のことが、作文教育研究でも指摘されている。下記エントリ参照)
そして、推敲という営みを、次のように表現する。
それは、漠然と感じていたことと、それをはっきりことばで表現してゆくこととのあいだに生ずる、絶えざる違和感の調整なのである。「わたしの考えていたことはこんなことじゃない」とか、「思ってもみなかったことが出てきたぞ、これはおもしろそうだから生かそうか」とか、ひとまず筆をおくまで、この綱引きはつづく。それ自身が生き物として増殖してゆくことばのちからと、同じく生きものとして、自分のなかの混沌に形を与えようとする書き手のちからとの、緊迫した綱引きである。(P214 )
このように、推敲を、目の前に生じたことばと書き手である自分との対話・相互交渉としてとらえ、その結果として確定する自己が現れてくるというのだ。
Discovery Writingを唱える本
本書の自己発見・自己創造の現場としての作文論は実に面白い。というか、端的に僕の好みでもある。例えば、この本と同じく優れた文章論と言っていい、細川英雄『自分の〈ことば〉をつくる あなたにしか語れないことを表現する技術』では、自己創造に他者の存在が不可欠とされていた。僕は前にそこへの少しばかりの違和感も書いている(下記エントリ参照)。
一方、本書では、自己創造はメモを現場とする自己内対話であって、そこに他者に開かれる必然性がない。書くこととは、書かれたことばと自己の交渉によって自己を発見していくことだ、という姿勢で貫かれている。細川本と本書のそのような世界観の違いは、どちらが正解というものでもあるまい。どちらも正解を含んでおり、どこに重点を置くのかの違いである。
しかし、僕個人は断然こちらの本のほうが好きだ。Discovery Writing(発見のために書く)の立場から、書くことについて真っ向勝負で切り込んだ本書は、いま読んでも得られるものが多い。僕は、かつてもこの本を「面白い」と思ったが、今ほど「すごい本だ」とは思っていなかった。もしかして作文教育に関わる経験が一定以上ある人ほど共感しやすいのかもしれない。いや、単純に、気づくのに僕の時間がかかっただけで、最初から軽々と本書の価値に気づく人もいるはずだ。いずれにせよ、近年の「文章の書き方本」とは一線を画する表現論である。ぜひ一読をおすすめしたい。
[ad#ad_inside]
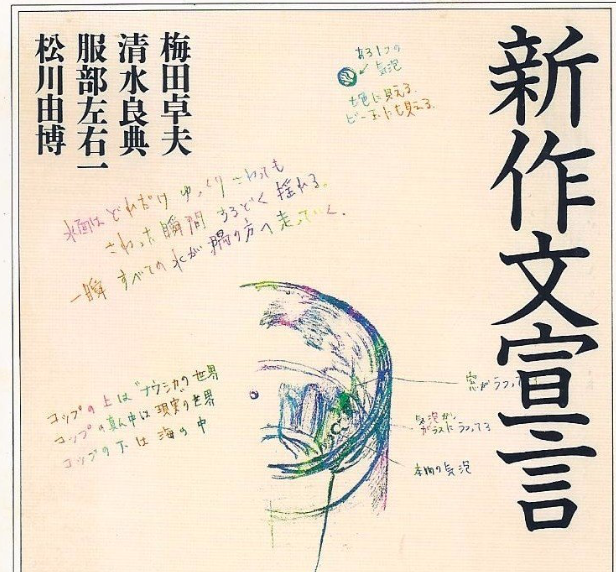

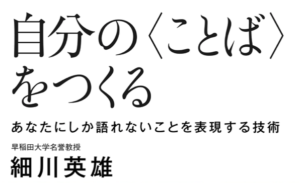


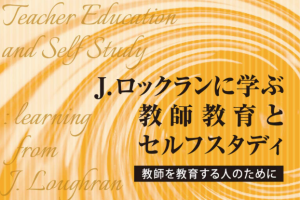





![[留学日記番外編]長女の留学をきっかけに読み直した「いつか、世界のどこかで」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/05/2015-09-19-16.50.58-50x50.jpg)
![[読書]文末表現に特化したユニークなレトリック本。瀬戸賢一「書くための文章読本」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2020/01/スクリーンショット-2020-01-07-22.21.16-50x50.png)