今日は外部から小学校の先生たち合計3名が見学に来校。行事前でどうしても一区切りつけざるを得ず、ドタバタに詰め込んでしまったダメダメな授業だったのだけど、そんな中でも考えさせられることがあった。
大福帳のコメントから
いま、高校の現代文ではエンハンスメントを題材にパラグラフ・ライティング形式で小論文を書こうという授業。パラグラフ・ライティングの書き方のメリットとして、先週、
- 構成が決まっているので読者には読みやすい
- 特に、パラグラフのトピック・センテンスを拾って速読することが可能になる
- 書き手も、事前に構成を考える必要があるので、書きながら考えた結果内容がぐちゃぐちゃになることがない。
ということを話したところ、大福帳で、「自分も文章を書きながら内容を考えてしまうところがあるから直そうと思った」という感想が、複数の生徒からあった。
実際の「良い書き方」はケースバイケース
ところが、僕が下記エントリなどで書いたように、実際は「書きながら考える」こと自体が悪いわけではない。むしろそれはDiscovery Writingと言って、考えを深めたり新しいアイデアを得たりするための重要な書き方の一つである。パラグラフ・ライティングとは親和性が低いというだけで、何が良い書き方かはケースバイケースなのだ。
それなのに、自分の発言で「書きながら考える」こと自体が悪いと誤解させちゃった可能性があるので、今日の授業ではフォローしておいた。「パラグラフ・ライティングはあくまで書き方の型の一つで、いつでもどこでも絶対にいい書き方というわけではないよ」「実際の英語の論文も厳密なパラグラフ・ライティングで書かれているわけではないよ」「そもそも、論文を書くのが仕事の人でさえ、みんなが事前に構成をしっかり練るわけじゃなくて、書き方は色々だよ(下記リンク先参照)」みたいな話だ。
「注釈」をいつ入れる?どこまで入れる?
文章について教えるときに、今回のような「実際はそんな単純じゃなくてね…」という「留保条件」を言いたくなることが、以前よりもずいぶん増えてきた。これは、ライティングについての僕自身の知識が増えたことに由来するのだろう。多くの研究が示唆するのは、実際の文章の書き方は書き手の個性に応じて様々だし、書き手としての成長も人により様々だ、ということだ。単線的な発展ではない。いつでもどこでも通用する「素晴らしい文章の型」があるわけでもない。そういうことを知ると、「型」を教えていてもどうしても「注釈」を入れたくなってしまう。
ただ、そういう「注釈」はどうしても授業のわかりやすさを損ねる。いちいちそういう注釈を入れていると、メッセージが明確でなくなるし、時間もかかる。生徒のモチベーションも下げるかもしれない。「注釈」を入れること自体が悪いこととは思わないけど、例えば、今は「型」やその効果だけ教えて、彼らが一回それで文章を書いて文章の形式を実感したあとに「実はね…」と切り出した方が、より効果的なのかもしれない。いや、それともやっぱり、大福帳でああいう反応があった直後の今回にすべきだったのだろうか。
いつ入れるか? どこまで入れるか? 授業で注釈を入れるにしても、やり方を考えないとな、というお話でした。






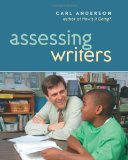







![[読書]2018年の個人的読書ベスト盤。未読の本があればぜひどうぞ!](https://askoma.info/wp-content/uploads/2018/02/still-life-3097682_640-50x50.jpg)