In the Middle読書日記。全600ページのこの本はざっくり300ページくらいで前後半に分かれている。前半は「Workshop Essentials」と題してアトウェルのライティング&リーディング・ワークショップの運営について書かれていて、313ページからは、第二部「Genre Studies」として、アトウェルの授業で扱う文学のジャンルについての解説および授業資料という構成だ。
▼
第二部の最初には、アトウェルが授業でどんなジャンルを扱うかという概略が書かれている。 面白かったのは、冒頭でいきなり「school genresは避ける」(p313)と宣言されていることだ。学校に特有のジャンル、ということだろう。ブック・レポート、5パラグラフエッセイ、夏休みにやったこと、などなど…。日本だと読書感想文や行事作文もこれにあたるかな?
アトウェルが書かせているのは、実際に書店や図書館にあるもの。詩、回想録、エッセイ、マイクロフィクション(ショートショートみたいなもの?)、新聞の論説….。生徒にとって魅力があり有用なものを重視しているらしい。
▼
ここの節で次のような記述があって目をひいた。
We are preparing students for work – and academia – by inviting them to write as children and adolescents write. (p315)
as children and adolescents writeという部分がイタリックになっている。子どもの時期に書くべき文章を生徒に書かせることを通じて、将来必要になる学問や仕事への備えとしている、ということだろう。ただの先取りはしないぞ、どのジャンルであれ通用する書く力の根本を育てるぞ、という意識がうかがえる。
▼
これは作文に限らないけど、大人はつい「子どもが年齢の想定よりも先に進んだ経験をすること」を称揚しがちだ。「小学生なのに、高校生が読むような本を読んでいる」「高校生なのに、大学でも通用する卒業研究」「世界を変える大学生起業家」などなど。
しかし、それは本当に価値があることなのだろうか。子ども時代には子供時代にやるべきことがある。例えば国語の授業で言うと、中高生時代に実用文の書き方、大学でのレポートの書き方、プレゼンテーションの仕方を学ぶことよりも、書くことを通じて自分の好奇心を傾けられる世界を見つけることや、自分では伝わると思っていたのに実は伝わらなかったという経験をすることのほうが、よほど大切なことかもしれない。僕もそのことは折に触れ自問していきたい。
[ad#ad_inside]

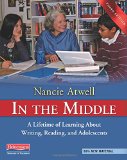





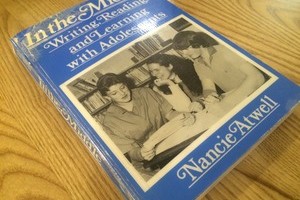



![[読書] 熱くて、静かな、行動する哲学者の本。國分功一郎「来るべき民主主義」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2017/04/スクリーンショット-2017-04-28-9.20.45-50x50.png)

