4月3日、国語探究研究会というグループのオンライン研究会で、『国語を楽しく』の著者である首藤久義先生(千葉大名誉教授。以下、「首藤さん」と書かせていただく)が、ナンシー・アトウェルのIn the Middle第二版を引用しながら読書教育論について語る会があり、知人の紹介もあって参加させていただいた。その会での首藤さんの主張が、ちょっと、というかかなり面白かったので、ここに感想を書いておきたい。(個人的メモなので正確な引用などはせず、大雑把な感想になる)。
[ad#ad_inside]アトウェルの文学教育批判とは
首藤さんが引用したアトウェルの著作は、僕が翻訳に関わった第三版ではなく、1998年に刊行された第二版のほう。この本の28ページ以降にある、文学教育批判を21ヵ条にわたって述べている箇所である。かつて僕はこの箇所を非常に面白いと感じ、それが大きなモチベーションになって、つたない英語力で毎日1ページ、30分ずつかけて読んできたものだった。残念ながら第三版からは削除されてしまったのだが、邦訳(抄訳)した『イン・ザ・ミドル ナンシー・アトウェルの教室』の前書きでも部分的に紹介させてもらった思い出の箇所でもある。
この日のオンライン研究会は、アトウェルのこの部分を引用しつつ、首藤さんが読書教育についてご自身の論を語られる、というかたちで進められた。
面白い!ラディカルな首藤さんの主張
その首藤さんの主張は、とてもラディカルで面白かった。大雑把な印象で言うと、首藤さんはダニエル・ペナックの「読者の権利10か条」そのものの方なんだな、という印象を抱いた。とにかく、「読書嫌いにさせない、あわよくば好きにさせる」ことを重視して、そこに向かって不要なノイズを一切消去するという感じだ。
具体的に面白かった首藤さんの発言を断片的に書くと、以下の通りである。繰り返すが、正確な引用ではなく、僕の理解であることは書いておきたい。
- 教師が教えて読みの力をつけることはできない。
- 「問い」を持って読むことを教えるのは、不自然である。子供が問いを持つときは自然に持つ。それでいい。(これは、いわゆる「問いづくり」の授業への批判だろうか)
- グループメンバーと折り合って読むことを強いるのではなく、一人で自由に読ませるべきだ。孤独とは、一人でいるかどうかではない。(これは、ペア読書やブッククラブなど、制度化された複数読みへの批判だろう)
- 本当に深く読んでいる子は通じない。語り合いたくない。学校で一緒に読むのは、他にも読んでいる子がいるということ。語り合いたい相手を選ぶことができないと、適当につきあうだけ。
- アトウェルの授業は、読むこと・書くことそのものがゴールになっている。
- アトウェルはそれほど先進的じゃなかったから評価された。
リーディング・ワークショップの教師は、僕も含めて、通常の国語の授業にあきたらず、読書教育をしている。だから、基本的には首藤さんの主張に非常に親和的である。それを前提とした上で、これらの発言から刺激を受けて、「なるほど!」「うーん」「そうかな?」と思ったことを書いておく。もちろん首藤さんご自身「私は極論を言っている」と明言されていたので、織り込み済みのものも多いかもしれない。
「教師が教えて読みの力をつけることはできない」
おそらく首藤さんの根幹にある理念。これ、本当にそうだろうか? いや、たしかにそうだ、と思う部分もあるのだが、例えば直接的な教授ではなくとも、環境や枠組みを整えることで子どもが読書に向かうことをうながすことはできる。また、アメリカの読書教育でも以前は「ただ読ませる」が主流だった時期もあるが、それだけだとやはり読む力の育成には効果的ではないということで、読むことの方略を直接的に教えるのが当たり前になっている。それは少なくとも「教師が教えて読みの力をつけることができる」という信念が前提になる行為だ。
この「読むことの方略」を「質問する」「予想する」「大切なところを見極める」などの「読書家の技」(すぐれた読者が使う方法)と称して教師が教えることは、日本でも吉田新一郎さんが紹介し、日本のリーディング・ワークショップ(読書家の時間)でも行われている。
ちなみに、アトウェルはこうした方略を教えることは読書への没入をさまたげるとして批判的だが、彼女だって教えないわけではない。文学用語について、有名な作家について、詩の中で用いられているテクニックについて…彼女は実はかなり多くのことを教えている。そして、その知識やその運用法をレター・エッセイでのやり取りを通して定着させようとしている。アトウェルもまた、「教師が教えることで読む力を伸ばすことができる」と考える人である。
で、僕も同様に考えている。何を「読む力」として捉え、それをどう教えるか、にはその時々のゆらぎはあれど、「読む力」を育てることができる、という前提は自分は捨てていないな、と感じる。もしかしてそれを捨ててしまったら自分が授業ができない、という「不安」がそこにあるのかもしれないが、まあ、子どもだけだけでなく僕自身が安心して教室にいられることも、授業をする上で大事な要素なのだ、と言ったら、開き直りすぎて元も子もないだろうか。
「問いを持って読むことを教えることは不自然である」
これは、文章を読むときに子どもたちが問いをつくって読む実践(いわゆる「問いづくり」の実践だろうか)への批判として、首藤さんが主張していたこと(発言はこのままじゃないはず)。教師が自分の解釈を明示的に押し付けるならまだしも、先生の望む問いを子どもに作らせる危険がある、という子どもの内面の自由を尊重される立場からの議論で、子どもの頃に先生の意図を忖度して自分の発言を操作していた僕としても、おおいに共感するところがあった(何しろ僕は、授業参観の時は先生も他の子に花を持たせたいはずだと思い、答えがわかってもわざとニアミスの回答をする小学生であった)。
この「問いづくり」だけでなく、先に紹介した「すぐれた読み手が使う方法」(読書家の技)の「予想する」「つなげる」…といった認知的道具も「そんなものを意識的に使って読むことを教えるのは不自然だ」として首藤さんが批判されるだろうことも、容易に想像がつく。これにも僕は基本的にシンパシーがある。自分が子どもの頃にそんなことを教わっていなくても、読書を楽しめていたし、経験を重ねて読めるようになったからだ。
ただ、一方で「自然な読書」を首藤さんが強調されると、ではその「自然」とはなんだろうとも思う。そもそも、話す・聞くと違って、読み書きは人間の「自然な行為」ではない。「識字率」という言葉の存在や人類の歴史が証明するように、人間は放っておかれたら読み書きができるようにはならない。読み書きは広い意味での「訓練」(教えられて、やってみて、できるようになること)の賜物である。
その上、学校というのは、制度としてその訓練の場という役割を、教師が好むと好まざるとにかかわらず、背負っている場だ。もちろん、できるだけ楽しく訓練してやりたい。しかし、それは本質的には「訓練」なのだという事実は、どうしても捨てられないのだ。
おそらく、読書を好きにする(嫌いにさせない)ことだけを目的にするなら、ペナックが言う「読みっぱなし。感想なんてわざわざ聞かない。言ってきた時だけ聞く」でいい。首藤さんもそう主張するだろう。でも、学校はそれで成り立つ場ではない。アトウェルも、ペナックの「読者の権利」を授業で子どもたちに紹介しながら、実際にはそれとは反することもかなりやっている(そもそも「読まない権利」が認められていないし、レター・エッセイを書かせているし、読書冊数を記録させている)。僕も同じだ。ペナックの読者の権利は好きだし子どもたちにも紹介するけれど、いろいろなことを教えるし、構成するし、評価する(もちろん「なにを、どう」教えて評価するかは、その時々で迷う)。それはすべて、首藤さんのおっしゃる「余計なおせっかい」であることに間違いない。それによって、面倒くさくなって読書が嫌いになる子もいるだろう。
でも、子どもは「好きー嫌い」の二軸だけを動機に動いているわけではなくて、「言われてやってみたらできるようになって好きになった」経験をする子もいる。僕は2023年度、それまで避けていた「読書家の技」を教えることにいったんふみきったが(これは、同僚のKAIさんが「読書家の技」を教える派で、真似をしてみたのだ)、「この技を教えてもらって、これまであまり感想が書けなかったのに書けるようになって、うれしい」という子も、確実にいた。その子にとって、「読書家の技」は自分の成長をうながすものとして作用したのだ。もちろん、その裏で「こんなの使って感想を書かされるのはめんどくせー」という子もけっこういたのは間違いないが。つまり、いろんな子がいるのである。だから、いろんな手を打っていい。すべての手がすべての子に最善になることはないが、そんなことはそもそもありえないのだし。
学校での読書は「自然な読書」ではいられない。しかし、そもそも人間が本当に「自然に」読んでいるなんてことはない。だとしたら、首藤さんの理念は理念として受け止めた上で、実践上は「自然」であることにこだわりすぎなくてもいいのではないか。自由な読みを称揚して、楽しくたくさん読めることを基本的には大事にしながら、時に「今回はこんなふうな切り口で読んでみよう」「今回は感想を書こう」と働きかける。そんな矛盾があっていいのではないか…と、現段階では思っている。
「一人で自由に読ませるべきだ」
首藤さんは、自然発生的に出るものをのぞいて、ペア読書やブッククラブをすることに批判的なようだ。一人で自由に読むこと、話したいときに話したい人だけで話せば良いことを強調している。特に、「語り合いたい相手を選ぶことができないと、適当につきあうだけ」という指摘には、僕自身もよく感じることなので、納得する。
ただ、僕には一方で、ペア読書やブッククラブを熱心にやっている実践仲間もいる。例えばトミー(冨田明広さん)は、「読書家の時間の半分くらいはペア読書」とおっしゃっていた。そして、彼が語るペア読書の良さにも共感する。例えば、実際の教室には、「一人では本に向かえない子」は確実にいる。けっこういる。そんな子が他の子との関係性の力を借りて本に向かっていく機会が、ペア読書であり、ブッククラブである。僕も授業でそんな経験があった。読書が苦手な子が、同じくらいの読書レベルの友達と一緒に読むことで、読書が楽しくなった経験である。そういう良さは実際にあって、他の人と一緒に「読まされる」ことを苦痛に感じる子ばかりでは決してない。
少なくとも一度はペア読書やブッククラブを全員で経験しない限り、「誰かと読む楽しさ」「本について感想をおしゃべりする楽しさ」を子供達は経験できず、それが自由に読むときの選択肢に登ることはない。そういう選択肢を一度は経験する意味で、ペア読書やブッククラブをすることは、決して悪いことではないと思う。
「アトウェルの授業は読むこと・書くことそのものがゴールになっている」
これは、アトウェルの、というよりライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップを、首藤さんが唱える「同時異学習」の枠組みと比較しておっしゃっていたこと。そう、たしかにそうなのだ。ライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップは、選択の余地は大いにあるが、ゴールが読み書きであることからは逃れられない。そして、「ゴールが読み書きであること自体が嫌」という児童・生徒は、教室に確実に存在する。アトウェルほどの力量のない僕は、そういう児童を惹きつけられていない現状だ。そういう子には、「本人にとって楽しいプロジェクトをやるために読む/書く活動をする」という枠組みのほうが有効のはず。あ、これは首藤さんの本『国語を楽しく』をもう一度読まないとな…と思った瞬間だった。この発言のおかげで、今年、またちょっと授業を見直せるかもしれない。
「アトウェルはそれほど先進的じゃなかったから評価された」
これは個人的に一番ウケた一言。たしかに、「自然な読書」ではないことも含めて、学校という制度の中で読書を授業として行うには、先進的すぎてはいけないのだ。彼女には「読者の権利10ヵ条」を標榜しながら、それに反するおせっかいをする「中途半端さ」がある。しかし、それこそが彼女の授業を支えている。とても的確なアトウェル評だと思う。
とても面白い研究会でした!
ここでは、思ったことや感じたことをつらつらと書いてしまったが、とにかく首藤さんは立場が一貫していて、話を聞いていてとても爽快なものがあった。刺激的だった。来週4月10日も続きがあるようなので、楽しみに参加したい。急な仕事が入ってきませんように!
[ad#ad_inside]

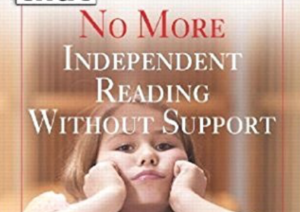

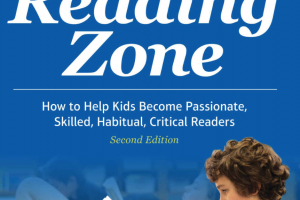

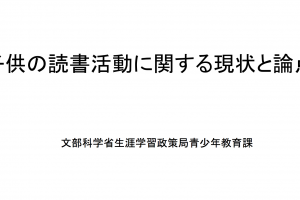




![[お知らせ]ひつじ書房ウェブマガジンに寄稿しました。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/05/IMG_4840-scaled-50x50.jpg)
