今日は、大阪で作家の時間・読書家の時間を大規模展開している中学校まで授業見学に行ってきた。何より、担当する先生方がみんな自分の書いた作品でデモンストレーションをやっている素敵な学校だったのだけど、その学校のことはあまりここに書くまい。その代わりに、帰りの新幹線の時間を使って、昨日の下記エントリの続きを書いてみた。というのも、下記エントリを読んで下さった方とSNSで少しやりとりして、そこでも少し発見があったからである。というわけで、今日も昨日の続き的な、自己分析系のエントリになる。
さて、昨日更新したエントリで、僕は自分自身の授業について、「国語の力をつけるために丁寧に場をデザインしてコントロールするタイプなので、その場に乗れる子にとっては力のつく授業になるが、その場に乗ることが難しい子には、僕の授業はしんどくなる」と書いた。では、なぜ僕はそのようなタイプになるのだろう。僕の授業づくりのエネルギーの源泉はいったい何なのだろうか。
「作家の時間」「読書家の時間」への探究心
おそらく一番大きいのが、僕の関心が、「作家の時間」(ライティング・ワークショップ)「読書家の時間」(リーディング・ワークショップ)という実践そのもの」に向かっていることだろう。それこそ、「子供を育てたい/教育したい」という教育欲よりも、「この実践がどういうものか知りたい」という探究心が僕の駆動力となっている。
この興味は僕の生育歴とも密接に関係していて、僕は学校の国語の授業で読み書きの力をつけたというよりは、自由に読み書きを楽しんだ結果として勝手に国語の力がついていたタイプなのだ(下記エントリ参照)。だから、僕のこの実践への興味関心には自己探究の側面もある。あまりこう書くと言葉で自分を縛りかねないが、僕の人生と作家の時間&読書家の時間という実践はかなり結びついたものであり、今のところ自分がこの実践を止めることはちょっと考えられない。
もちろんこの探究心には良し悪しある。一番の弊害は「子どもよりも個人的探究心を優先してしまう」ことだ。「子どもにとってベストの国語教育は何か?」ではなく「作家の時間や読書家の時間がどんな実践なのか知りたい」から出発して、そのレンズを通して子どもを見ているので、子どもを自分の関心のど真ん中に置くことはない。ゴリさんはよく「はじめに子どもありき」と言っていて教師の鑑だと思うが、そもそもデモシカ教師からはじまった僕は、確実に「はじめに自分ありき」である。
とはいえ、実践への関心と子どもへの関心はゼロサムの関係ではない。僕がそこからスタートしたことは嘘ではないが、教師を志して教師になった人と決定的な差があるのも事実だろうが、でも、この実践を続けていれば子どもの個に触れる機会は増えるし、単純接触効果もあって、以前よりも僕は「子ども」への関心が強まっている。また、「作家の時間」「読書家の時間」の実践に親和的ではない子への許容度も風越に来てから高まっていると思う。つまり、実践への関心を軸にして子どもへも関心を広げつつあるところであり、これはとても良い傾向。
一流の実践者に対する憧れ
もう一つ僕を駆動しているのは、一流の実践者に対する憧れである。これは多分にミーハー気分も含んでいる。一流の実践家と呼ばれる人たちがどんな思考をしているのか、どんなふうに世界を見ているのか、それを知りたい、その世界を見てみたいという気持ちだ。僕の私淑するナンシー・アトウェルが、ティーチャーとファシリテーターの間を行ったり来たりして、その都度自分の本を大幅に書き換えるような教師人生を歩んでいなかったら、そんな彼女の人生に僕が出会わなかったら、僕の教師人生は全く違ったものになっていただろう。
アトウェルは特別にせよ、甲斐利恵子や石川晋、それからいつもの勉強会の仲間など、「この人は本物だ」「この人は尊敬できる」と思う人との出会いによって、「この人にはどんなふうに見えているのか?」を知りたくなり、僕の世界は少しずつ広がってきたと思う。
そして風越学園に移ってきたおかげで、その対象が、風越の同僚をはじめ国語教育系ではない人にも広がりはじめている。ファシリテーションやプロジェクト・アドベンチャーなど、かつては全く興味のなかった実践を高いレベルでやっている人が身近にいることは、僕の国語教師としての今後にもプラスになると期待している。
真面目さ、職業的義務心の強さ
3つ目。これは、よくいえば「真面目」とか「プロ意識が強い」ということにもなるのだが、僕の職業的義務心というか、「仕事なんだから、興味がなかろうがタスクはやらねばならない」という気持ちが、僕は結構強いタイプのようだ。これも風越学園に来てはじめて自覚したことである。例えばテーマプロジェクトとかいまだに興味はないのだけど、ひとまず仕事だからという理由だけで仕方なくやってしまえる面がある。子ども対応や保護者対応も然り。結果、仕事が増えて残業も多いので、「賃金分をきっちり働く(それ以上は働かない)」という意味では全然プロ意識がなっていないのだけれども。
この僕の真面目さ、あるいはプロ意識の強さは、僕の職能を広げてくれるものでもあるが、当然諸刃の剣でもある。例えば、作家の時間でまるで書かない、読書家の時間でまるで読まない子がいた時に、僕自身の力でなんとかしてしまいたくなるのは、僕の持つ真面目さが悪い方に出ているからなのだろう。そういうとき、子どもの方では別に「なんとかされたい」なんて思っていないのだから。
また、ついうっかりして、自分と同様のコミットを同僚にも求めないように注意しないといけないな、とも思っている。「仕事なんだからちゃんとやる」「そのくらいはやらないといけない」の「ちゃんと」「ねばならない」の水準が、きっと僕は通常の人よりも高いタイプなのだ。それを無意識に押し付けられたら、同僚もたまったものではないだろう。
「ちゃんと」や「ねばならない」ができてしまう僕は、その「ちゃんと」「ねばならない」を子どもや同僚にも無意識に期待してしまう傾向がある。それは悪くすると、僕がいる場の雰囲気を息苦しいものにしてしまう。その傾向を自覚して、「ありのままでいい」「適当でいい」ということを、僕は自分にも人にももっと認めていかねばならない。(と、ここでも「ねばならない」思考で動くので、これはもうどうしようもないのだ)
「書くことで距離を置く」つもりで…
二日間にわたって、なんでこんなことを長々と書いているのか、自分でもそろそろわからなくなってきた(笑)。でも、自分自身の性格、感じ方、関心は、いずれも自分の授業を形作っている大きな要素だ。だからこうやって言語化することは、ふだんは透明になっているこうした要素を対象化する上で、必要なことに違いない。
ただ、それは効果もある一方で、逆に文字にすることで「自分はこういう性格だから仕方ない」という形で自己物語を強化・固着化する危険も伴う。だから、僕自身、ここに書いたことをあまり絶対視せずに、「書くことで自分から少し距離を置く」くらいの気持ちで、気軽にここにポンと置いておきたい。
[ad#ad_inside]






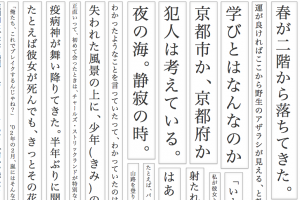
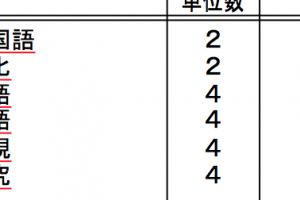



![[読書]小山田浩子「穴」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/4106oj5pl3L._SL160_-50x50.jpg)
