昨日、たまたま(というかようやく?)風越学園の前期スタッフ・遠藤綾さんが前職時代に書かれていたエッセイ「馬先生 わからないものと出会うこと」を読んだ。家族まるごとの馬との関わりの中で、自分の当時の仕事での悩みやこれまでのあり方をふりかえる、読み応えのあるエッセイだった。読み終えて、この文章と直接関係はない内容なのだけど、最近つらつら考えていることを書いてみようという気になった。
森と国語教育?
身内びいきのような発言になるが、主に森の周辺で日々を送る風越学園の前期スタッフには、素敵な文章の書き手が多い。時に相手と同化し、時に距離を置くような、子どもを見る眼差し。自然の移ろいへの細やかな観察眼。一人ひとりの声を感じさせる文体。それらが何によってもたらされているのかはわからないのだけど、彼らの書いた文章を読んでいるうちに、「森と国語教育」という思いつきが、ふと浮かんできた。
森には、日々の変化がある。一日の流れが太陽の光や影を通して伝わり、四季の移ろいも、葉の一枚一枚の変化や、空気の凍るような冷たさで体感される。時間の流れを、時計なしでも感じ取ることができる。また、森にはちいさな生と死がある。春になると出てくる動物の足跡、ハルゼミの声、蛇の抜け殻、草の陰でいつの間にか死骸となった小さな虫たち。時間の変化と、生死。ここにはナラティブの原型があるのだ。物語は、人間が自然と暮らす中で、そこで出会う不思議や理不尽を、自分たちなりに意味づけ、理解するものとして生まれてきた。神話などの例を見ても、おそらくそう言っていいのだろう。森には、物語の鋳型がある。
また、森の中には日々のちいさな変化がある。ひとつひとつは、言葉にもならないちょっとした変化。昨日よりも少し雪が重たいとか、風があたたかくなったなとか、ざっくりと落ち葉を踏む時の感触が違うぞ、とか。森の中で日々を過ごすとは、コントロールできない自然に対応して、自分の感受性の網の目を細かくしていくことだ。この感受性の網の目に、いつか、ひとつひとつの言葉が対応したとき、どんな言葉の書き手になるのだろう、と思う。
「春のうた」の授業で…
もう去年の春のことだが、草野心平の詩「春のうた」を風越の国語の授業で扱ったことがある。その詩を読む中で、「おおきなくもがうごいてくる」という行に出てくる「くも」が、「蜘蛛」か「雲」かという話が出た。その時に、軽井沢出身の、生き物好き・昆虫好きのある子が、「実際の蛙はこうだから…」と語っていたのが印象的だった。それは、単に、蛙の眼の位置についての知識があるというのとは違う、まるで自分が蛙の立場になったような語りぶりだったのだ。
それは、僕が長年教えていた東京の優秀な生徒たちの反応とはちょっと違って、蛙と身近に接している人間ならではの読みだった。「自然の中で暮らす子たちは、こういうふうに読める可能性があるのか」と驚いたのを覚えている。自分が蛙になったように生き生きと解釈を語る姿は、なかなか東京ではお目にかかれないだろう。
森とライブラリーをつなぐ
森の中の、時間の流れや季節の変化を肌で感じる生活。様々な生き物の生と死のそばにいる生活。風越の子たちは、物語を学ぶための豊かな素材に囲まれている。それに語彙が後からついてくれば、国語の力に結びつかないわけがない。これは全く妄想の域を出ないのだけど、僕は最近そう思いつつある。森で物語への感受性や眼を育て、ライブラリーでたくさんの物語に出会い、言葉を獲得していく。森とライブラリーによって育つ言葉の力。
森とライブラリー。風越学園の大きな財産であるこの2つの柱は、今はまだ有機的に結びついてはいない、と僕は思う。森は前期の園児たちが主に過ごす場所であり、ライブラリーは後期の子が過ごす校舎の真ん中にある。つまり、前期の子はライブラリーと十分につながっていないし、後期の子は森とつながっていない。
でも、彼らの中で、この2つがきちんとつながったらどうなるだろう。森での日々で培う物語への感受性や観察眼が、ライブラリーでの「読書家の時間」で出会う物語や、それを表す言葉と結びついたとしたら。そして、その2つの出会いが、「作家の時間」で子どもたちが自分にとって大切な物語を創り出す言葉を生み出すとしたら。残念ながら、ぼくにはまだその情景がくっきりと描けていない。でも、森とライブラリーをつなげることは、「作家の時間」「読書家の時間」とならんで、風越学園ならではの国語の授業のあり方を考えたときに、わりと大事な要素のように思えるのだ。
[ad#ad_inside]



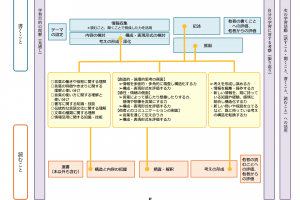







![[読書]穂村弘・山田航『世界中が夕焼け 穂村弘の短歌の秘密』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/41xadgCiClL._SL160_-50x50.jpg)

