▼
ここまで読んでわかったのは、第3版でのアトウェルが自分の教育姿勢を表す重要な鍵概念として、「handover(手渡す)」 という言葉を使っているということ。
私はhandoverという言葉が好きだ。それはこの言葉が、大人と子どもの間にある生産的な人間関係が持つしなやかさを暗示するから。 それはhandoff(手放す)ではない。大人は行動的で、子どもを導きながら仕事をする。handout(配る) でもない。子どもも行動的で、意図を持ちながら仕事をする。…私たちはどちらも熱中している。 ….私がアンを教える時、彼女は私を見、私は彼女を見る。私はやってみせ、彼女は挑戦する。私たちは語りあい、やがて彼女が私をもう必要としなくなるまで、私は必要な時に彼女を助ける。 p15
アトウェルはこの自分の態度を、In the Middle初版(1987)の頃の自分の姿勢、つまり伝統的な一斉授業の教え方を否定して教師がファシリテーターに徹するワークショップ型授業を提案した頃の自分の姿勢と比較して、次のようにも述べている。
ここには、伝統的な教え方も、その否定もない。子どもの意思と大人の介入に充ちている。そして、私がライティング・ワークショップを始めた頃の公式化されたファシリテーションとは違って、この方が人間同士の関わり合いとしてふさわしい。 p15
アトウェルは、自分の持つ豊富な読み書きの知識や子どもに関する知識を活用して、子どもに介入することをためらわない。デモンストレーション、ミニレッスン、個別のカンファランス…さまざまな場面を通じて教えていく。
▼
例えば、アトウェルがultimate version of handover(handoverの究極の形, p114)と呼んでいるミニレッスンがある。それはライティング・ワークショップのカリキュラム初期に行われる複数日にまたがるミニレッスンだ。
(1) アトウェルが自分で書いた詩と、その詩を書くためのメモや下書き(全12枚!)を生徒に配る。
(2) 次の日に、生徒からその詩の創作過程についての質問を受けつけ、答える。
(3) アトウェルが創作過程で何をしたかを生徒に文章でまとめさせる。
(4) それをアトウェルがまとめ、加筆修正して「詩人が良い詩を書こうとする時に行うこと」というプリントにまとめる。
(5) 以後、このプリントは色々な場面で創作のヒントとして参照する。
In the Middle, pp109-114
これ読むと、まさに自分という存在をまるごと生徒に「手渡して」いく印象。自分で詩を書いて教材として使うのだから、モデルを示す最たるもの。ミニレッスンではこういう形で全体に向けて、個々のカンファランスでは個々の生徒に合わせて、アトウェルは常に書き手としてのモデルを示し続けている。
▼
この「handover」、アトウェルはこの言葉を、通常の教師がやる押しつけ的な「伝達する/配る」(handout)とは明らかに異なるニュアンスで使っている。でも実際どう違うのかなあとぴったりくる言葉を探していたら、たまたま読み返した別の本の一節がシンクロした。大村はまの教え方についての文章だ。
要は、形だけをとらえて論じても意味がない。目の前の子どもと教師との間で、どんなふうに型の伝授が行われているか、ということだろう。てびきを与える、口移しで○○○と言ってごらん、という、そこだけを見て判断できることではない。そのやりかたが、不器用で柔軟性や多様性に欠けていたら、押しつけになる。十分にこなれていて、その子どもをよくよく知っていて無理がなく、幅広くものを見ていて、生徒との信頼関係も成り立っていたら、生徒は押しつけとも思わずに、ああ、助かった、そうか、そうすればいいのか、そんなやりかたも会ったのか、と、そのてびきを存外すっきりした顔で受け取る。
そして、本当に適切に手際よく示されたてびきというのは、自然で、無理がないので、その存在感がかえって薄れ、子どもは自力で進んでいるような気持ちで学ぶ。教えられた、手助けされたという意識をあまり持つことなく、まるですべて自分の力で歩んでいるかのような気持ちで、堂々と学んでいく。大村が目指していたのはこういう手のひき方だった。苅谷夏子『大村はま 優劣のかなたに』p184
ああ、なるほどと思う。大村とアトウェルのやり方には違いもずいぶんあるが、生徒を理解した上で自分の手持ちの材料を全力で手渡し、生徒はそれを「押しつけ」ではなく自分にとっての必然として受け取っていくという点で、大村の手引とアトウェルのhandoverが目指していたものには、大きな重なりもあるのではないか。
ともあれ、このhandoverという言葉には今後も注目して読んでいかなくては。









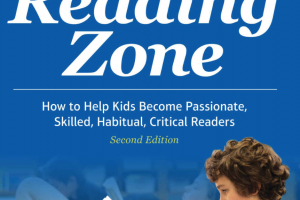


![[読書]デジタル時代に「深い読み」をいかに保つか?メアリアン・ウルフ『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/03/bdbdd584ca3a09c04316a3fc83987bb5-50x50.png)
![[読書]今年の授業を見直すきっかけになるかも?な、2024年3月の読書](https://askoma.info/wp-content/uploads/2023/12/a-book-6213537_1280-50x50.jpg)