藪下遊/髙坂康雅『「叱らない」が子どもを苦しめる』は、「子どもを叱らない」「褒めて伸ばす」「その子の意志を尊重する」風潮の強い近年の子育てによって、かつてとはタイプの異なる不適応が生まれているという仮説をたて、その実態への具体的な対応を提言する本である。著者はスクールカウンセラー。豊富な現場経験に裏打ちされた実践的な提言は、学校教員はもちろん、親をはじめとする子どもに関わる大人は必読と言ってよい。
[ad#ad_inside]指定図書の価値ある一冊
僕がこの本を手にとったのは、高校国語科教員のイマキヨさんという方がfacebookで「教職課程とか初任研の指定図書にした方がいい」と推薦されていたのがきっかけである。読んで、僕も「まさに」と思った。本書では、カウンセラーである筆者が、自身の臨床経験から感じた最近の子どもの不登校や不適応の理由の変化を述べ、その背景を分析して仮説をたてるとともに、そういう子たちにどう対応していくのかを、実に地道な実践例にもとづいて述べている。中には保護者とのやりとりの留意点など、きわめて具体的なアドバイスもあって、教員の指定図書にするだけの価値のある本だ。
「やりたいこと」を中核にする危険性
近年の不登校や学校不適応に対する筆者の「仮説」は次のようなものだ。最近の子育ては「褒めて伸ばす」「子どもの自主性を重んじる」が主流になっているが、それが「ネガティブなところを否定しない」や「子どもの不快を避けてあげる」にすり替わってしまうことが多い。そのため、幼少期から自分の「できなさ」や「不快」に向き合う機会(筆者は「世界からの押し返し」の機会と呼ぶ)が減っている子どもは、万能の自己イメージを保持してたまま、未成熟な状態で成長してしまっている。そのため、自分の理想イメージと異なる自分が受け入れられなかったり、思い通りにならないと我慢できなくて、逃げ出したり、他の人のせいにしたりして自分を守ろうとしてしまう…。
こういう構図に思い当たる人は多いのではないだろうか。例えば、風越学園のスタッフや保護者のうちには、次の表現にドキッとする人もいると思う。
そもそも子供時代というのは、「できること=可能」を開拓・拡大していく時期です。自分は何ができるのか、為すことができる範囲はどの程度か、そういうことを知る時期なんです。だからこそ、学校を始めとした社会の中では、子どもに「まだ知らないこと」を教えるし、「できないこと」でも頑張ってやってもらおうとするわけです。そういう活動を通して、子どもの「可能」を開拓・拡大するというのが学校の機能の一つなんです。
この時期に「やりたいこと=願望」を中核にしてしまうと、可能の範囲を知らずに「できる」と勘違いしたり、未知のものを「やりたくない」と子どもの快不快だけを基準にして排除してしまう恐れがあるのです。(pp141-142)
特に、「「やりたいこと=願望」を中核にしてしまうと、可能の範囲を知らずに「できる」と勘違いしたり、未知のものを「やりたくない」と子どもの快不快だけを基準にして排除してしまう恐れがある」という指摘は、やりたいことを尊重する風越学園に勤めている僕としては、おおいに共感するところだ。
ネガティブな感情をどう取り扱うか?
ここまで書くと、なんだかひと昔以上前の「自分の主張をする前にまずは言うことを聞け」とか「叱って育てろ」派が溜飲を下げるような本に思えるが、全くそんなことはない。というのも、筆者が主張しているのは、「世界からの押し返し」にあった時の子どもの不穏感情(ネガティブな感情)を大人も一緒になってきちんと取り扱うことであり、単に叱るだけでは、それができないからである。
そして、本書の最もすぐれた点は、ここまでに書いた原因の分析(仮説)ではなく、第4章「子どもが「ネガティブな自分」を受け容れていくために」や第5章「予防のための落ち穂拾い」に書かれた、「では、そういう子たち(やその保護者)にどう向き合うか」という点にある。ここを詳述してしまっては著者に申し訳ないので、ぜひ手にとっていただきたい。これらの章では、基本方針からはじまって、具体的な方法、学校との関係がこじれやすい家庭への対応、支援の落とし穴や予防にいたるまで、きわめて具体的かつ実践的な論が続く(この予防に「辞書を引く」があるのも意外な文脈だけに面白かった)。この方面の練達の方なら「ああ、たしかに」程度なのかもしれないが、僕にとっては勉強になることばかり。風越もご多分に漏れず具体的なケースはたくさんあるだけに、ここも、ぜひ同僚と一緒に読んでみたい箇所だ。
子どもの「社会化」のために
学校の機能の一つが子どもの「社会化」にあることは間違いない(その機能がなければ、そもそも国家は学校教育に公的資本を投下せず、受益者負担ですむ話だ)。「社会化」とは、少なからずストレスのある外界に自分を「合わせること」を意味する。その合わせる先の「社会」を、どの程度教育による可変性があるものと考えるか、それによって本書の受け止め方は多少異なるかもしれない。しかし、どちらにせよ、子どもが社会の中で生きていくことは間違いないし、そこには当然「思い通りにならない」さまざまなできごとがある。そうした「思うに任せないこと」を受け止める粘り強さをどう育てるか、本書はそのための具体的で有益な指針となる。
[ad#ad_inside]
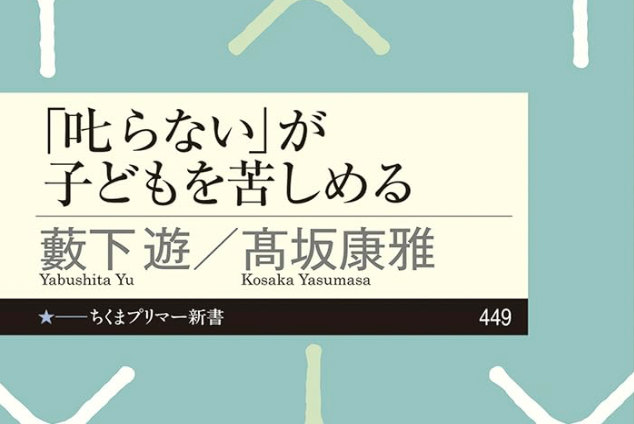


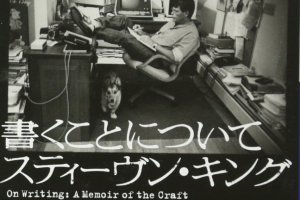
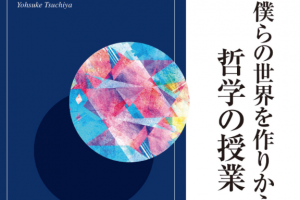

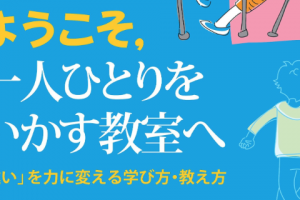



![[読書]「読む−聞く」営みを、場づくりの真ん中に置く。石川晋『「教室読み聞かせ」読書活動アイデア38』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/06/3ef4e802fc1a3312c01ff73c31949713-50x50.png)
![[読書]作文教育の本から、コミックエッセイまで幅広く。2024年2月の読書](https://askoma.info/wp-content/uploads/2023/12/a-book-6213537_1280-50x50.jpg)