先週末の9月15日、日本教育心理学会のシンポジウム「知見の統合は何をもたらすのか」に登壇してきました。ここでの「知見の統合」とは、エビデンスの質が最も高いとされるRCT(ランダム化比較試験)の研究のメタ分析のこと。ハッティのこの本がとても有名で、日本でも評判になりました。
僕は完全に門外漢ながら、現場教員の一人として「知見の統合」についてどう思うかお話させていただいたわけです。今日のエントリは、その振り返りを兼ねて、「エビデンスに基づく教育政策」についていま自分が考えていることをまとめてみます。少し長い備忘録です。内容的には、下記エントリを踏まえていますので、よかったらそちらもどうぞ。
[ad#ad_inside]「知見の統合」は現場とどう関わるか?
まず前提として、文科省が今後エビデンスに基づいた教育政策を進めること自体は疑いようがありません。すでに、下記リンク先のように、エビデンスに基づく教育政策についての調査が進んでいます。
教育の市場化・自由主義化の流れの中で、おそらく「エビデンスのないことにはお金を出さない」という緊縮方針を支える政治的方便としても、「エビデンス」という言葉は今後ますます使われるでしょう(少人数制学級に対する財務省の見解が典型的ですね)。また、そのような皮肉な見方とは別に、メタ分析のようなエビデンスの質の高い研究成果が信憑性が高いことは事実なのだし、学界として教育政策に貢献する機会にもなるので、取り入れるべきだ、と推進する考え方も当然あるでしょう。
僕も、特に文科省などの大きな教育行政のレベルでは、エビデンスの質の高い研究の成果(=知見の統合)は無視しない方が良いと思います(ただ、どう扱うかは大きな問題かとも思います)。ただ、僕の関心は現場にあるので、現場ではこの「知見の統合」にどう関われば良いのか、が気になるわけです。
「どのように考慮すればいいのか?」問題
ここでまず僕にわからないのは、質の高いエビデンスを現場でどの程度考慮すれば良いのかということ。僕の理解では、知見を統合した結果はあくまで全体的な傾向性を示すもので、成果をもたらす要因もそれだけではわかりません。したがって、国や地域の教育行政レベルでは「たぶんこうした方が良さそう、少なくともひどい結果にはならなそう」と言えても、学校や授業やクラスといった小さい単位については、個別の要因があり過ぎてそのまま成り立ちません。でも、僕たちがいるのはまさにその「学校」「授業」「クラス」といった小単位なのです。
自分の職場を例にすると、軽井沢風越学園でやろうとしている「異学年・異年齢学級集団」も「学習者自身による学習管理」も「学習者中心の探究学習」も、ハッティによる分析ではいずれも効果量が低く、少なくとも学力面での効果は非常に疑わしい。では、風越学園はそれをやるべきではないのか?とは直接にはならない。学校の設立理念(教育は何のためにあるのか)とか、時間割とか、集まってくるスタッフの熱意とか、色々な個別の理由があれば、全体的な傾向など覆してしまうかもしれないからです。
では逆に、「全体的な傾向は個別の現場にはすぐには当てはまらないのだから、まるっと無視して良いのか」というと、それも違う。自分がやりたい&信じたい教育実践を支える研究を「エビデンス」として正当化の根拠に使い、そうでない研究は「全体の傾向に過ぎないから」無視する、というやり方は、エビデンスの「恣意的なつまみ食い」であって、不誠実であるという誹りを免れません。ハッティも、教師が自らの好む「教師が教えるのではなく、生徒が自分で発見して意味を構築する」構成主義的な学習方法にとらわれ、むしろその逆を支持しているメタ分析の結果を無視してしまうことについては、批判的な論調でした。
イデオロギーを優先させて質の高い学問的成果を無視することは、僕もしたくありません。少なくとも、自分の実践がメタ分析ではどのように言われているのかを参照項として常に確認し、どういう時に自分がそういう知見に従うのか/従わないのかという判断基準は、常に問い直されないといけないでしょう。とは言え、現実に「では、具体的にどう考慮すればいいの?」というところで立ち止まってしまうわけです。だって、実際に「参照して頭の片隅に入れる」「自分がその知見の統合をなぜ無視する/しないのかに自覚的になる」以外に、特にやることが思いつかないのです…。
レトリックとしての「エビデンス」への警戒感
もう1つの別の問題として、教育現場では「エビデンス」という言葉があまりに広い意味に使われ、しばしば「エビデンス」という言葉が「科学的で正しいもの」として受容されるためのレトリックになっている現実があります。そもそも、エビデンス自体には高い低いもあり、最も質の高いエビデンスと言われるメタ分析の研究でさえ、あくまで全体の傾向を示すのみ。それなのに「これが科学的な結論だから、この通りにしなさい」のような、「強く正しい意味」を帯びて使われてしまう。
「これはエビデンスを産出する研究者の側の問題ではなく受容する側のリテラシーの問題」という研究者の方もいるでしょう。ですが、実際には文科省の方でさえそのリテラシーが十分とは言えない気もしています。
例えば、文科省の国語科の教科調査官の大滝一登氏は、6月の全国大学国語教育学会の課題研究で、高校の新学習指導要領に新井紀子氏の研究がエビデンスとして影響を与えていると発言していました(僕も登壇しており、すぐ隣で聞いていたので間違いありません)。ところが、新井氏の研究は、これまでのところ彼女のグループの研究に過ぎず、現状では決して「最も質の高いエビデンス」とは言えません。少なくともメタ分析ではないことは事実なので、仮に新井氏の研究が独自性や魅力や発信力を備えているにせよ、特定の1グループの研究に学習指導要領がそこまで簡単に影響されてしまうこと自体に、僕は危うさを感じました。
優秀な文科省の方でもそうなのですから、まして、僕たち一介の現場教員に、「エビデンスを受容するリテラシーを身につけよ」というのは酷な話ではないでしょうか。かくいう僕も、大学院でSPSSをいじった程度で、メタ分析に必要な統計の知識に欠けており、そこで実際に行われていることの意味を理解することはできません。
このことは、決して僕たちがリテラシーを身につけなくて良いと言うわけのではないのですが(そりゃああったほうが良いでしょう)、現実として統計リテラシーを身につけるのは極めて厳しいことには違いありません。そして、こういう教員・教育行政側のリテラシーの低さにつけこむ形で、研究者の中にも、現場教員に「これが科学的に正しさが証明されたやり方」という誤読を誘う形で自分の研究結果を提示する人が出ないとも限りません。そういう「レトリックとしてのエビデンスという言葉」の使われ方を想像するだけで、僕としてはどうしても「エビデンス」という言葉に警戒感を抱いてしまうわけです。
うーん、消極的な自分の姿勢…
上記のようなことを考えると、「知見の統合に現場がどう向き合うのか」と聞かれても、結局「うーん」と考え込みつつ距離を置く…という消極的な姿勢になってしまう。それが、現時点の偽らざる本音でしょうか。
色々と考えているうちに、今後の展開として、やや悲観的な予測もしてしまいました。例えば、教育政策に十分なお金がかけられない中で、「精選」の手段として「エビデンス」という言葉が使われることは十分ありそうだな、とか。
そしてこうなると、研究しにくい、長期的で様々な変数がある現象(教育ってそもそもそういう現象なのですが)は、エビデンスが集まらないので、問題として扱われにくくなります。「エビデンスに基づいた教育政策」を謳い文句に、教室内の長期的で複雑な現象が単純化され、短期的に成果が見込まれるものに予算がつけられる。年々予算が厳しくなっている大学研究者の中には、文科省の教育政策に乗って研究を進める方も一定数は出るでしょう。とすると「こんな介入をしたら短期的にこんな結果が出ました」という研究が増えて、ますますそういうエビデンスが蓄積され、公開される…。
さらには、本来は「全体の傾向」に過ぎなかったはずの公開された研究結果も、いつのまにか絶対視され、「エビデンスに基づいた科学的授業法」が喧伝されたり、各教育委員会レベルで「エビデンスに基づいた○○スタンダード」が設定されたりする。そして、僕たち教員はその通りに教えないといけなくなる…。
根っこは「教師教育」の問題?
性格の悪さがにじみ出る未来予測でした。上記は僕の偏見に近いので、事実誤認や理解不足もあるでしょう。こんなことになるはずないよ、という専門家の方からの指摘は、むしろ積極的にお待ちしています。
とにかく、エビデンスに基づく教育政策が、僕たち現場教員の自律性を損なわない形で導入されることを祈るばかりです。そして、この問題の現場にとっての根っこは、「教師教育」なんだろうなあとも思います。「エビデンス」という言葉に踊らされないリテラシーというだけでなく、そもそも僕たち教員が日々研鑽を積んで実力を磨き、周囲から信頼されているのであれば、こういう意地の悪い未来予測は実現しないと思いますから…。
[ad#ad_inside]


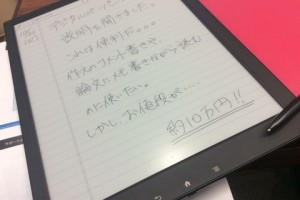





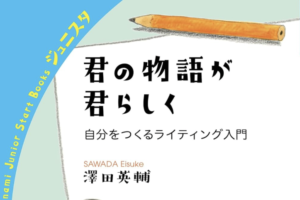


![[読書]するりと入り込んでくるような。原田マハ『あなたは、誰かの大切な人』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/09/Screen-Shot-2016-09-12-at-10.20.00-50x50.png)