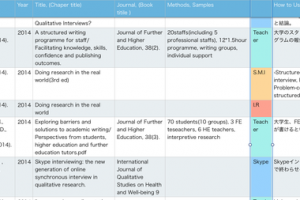高校でのライティング・ワークショップ。今シーズンは見学の方も多く、その方々とほぼ毎回、授業後に振り返る会を行なっている。その場で話しながら「あ、自分はこんな風に思っていたのか」という発見もある。先週はメディアリテラシーを専門にする大学の先生がいらしていたので、授業後の会で「オーディエンス」(ここでは読者)の性質が話題になった。
[ad#ad_inside]
「教室の外の読者」と「真正な場」の関係
その先生の質問は「この授業で書いたものの読者はクラスメートを想定しているようだが、夏にコンクール等への応募を奨励するときは外部の読者を想定している。オーディエンスをどう使い分けているのか」という趣旨だった。僕は確かにこの授業では外部に読者を用意することはあまり重視していない。そこから、真正な場とオーディエンスの関係について思うところがあった。
よく、書くことの教育では「真正な場」を用意することが大事だと言われている。そして、その時の「真正な場」とはほぼ「教室の外に読者を用意する」と同義になっている。教室の外に読者がいることで、生徒は本気になって書く。なるほど、そういう経験は確かに少なからずある。
ただ、確かに僕のこの授業では読者を外部に求めることをさほど重視していない。それは、単に余力がなくてそうなのかもしれないけど、どうもそれだけではないらしい。Discovery Writing(書くことが自分にとって発見となるような体験)を生徒に求める僕は、どうも最近、その発見を外部の読者に伝達することへの意識が、ちょっと弱くなっているようなのだ。これは、書くこと自体が外部の読者を前提とした行為であることを考えると、あまり良いことではないかも。
ただ、一方で「教室の外に読者がいること」イコール「真正な場が成立している」わけでもないはずだ、と思う。教室の外に読者が設定されていても、その場の設定が完全に教師主導であり、「読ませたくない読者に向けて書かねばならない」状況であれば、それはその生徒にとっては全く真正な場ではない。例えば中1の終わりに、「新一年生に向けてこの学校を紹介する新聞を書きましょう」という単元を設定しても、別にそんなことに興味のない生徒にとっては、どうでもいい話である。
自分の読者を自分で選べること
もちろん、「教室の外に生徒がいること」は多くの生徒にとって「真正な場」を構成する要素の一つになりうる。だからその要素は大事だ。ただ、それのみが「真正な場」を構成するわけでもないし、生徒が本気になって書く「真正な場」を作るには、他にも色々な要素がある。本当に書きたい話題であるかどうか、書きやすい環境が、選択できる環境が整っているかどうか、適切なサポートがあるかどうか…。
読者の設定に関していうと、「教室の外に読者がいること」以上に、「生徒が自分の読者を自分で選べること」の方が大事ではないか、と最近の僕は思う。書いていることが書き手にとって本当に興味深い問題であれば、時に、自分一人が読者の文章だって、真正な場になりうる。これに関していきなり恥ずかしい過去を書くようだが、僕は中学高校時代に毎日30分くらい大学ノートに書き物をしてから寝る習慣があった。あれは誰かに見せる文章ではないが、僕にとって「真正な場」だったことに間違いはない。
大村はまの「実の場」が成立する条件とは…
ところで最近、大村はまの実践を再訪しているのだけど、「国語教育」2017年4月号の「大村国語教室に学ぶ授業づくり・環境づくり」という特集を読んだら、今回の話題に関連する話題もあった。苅谷夏子「「実の場」を取り入れた授業づくり」という論考である。この中で苅谷さんは、「実社会との設定があれば「実の場」になるわけではない」ことを強調している。そして、大村はまの教室で「実の場」が成立していた構成条件として、次の二つをあげている。
- 取り組み自体が新鮮で魅力的で、手応えがあること。過去に先輩たちもさんざんやった「お古」や「二番煎じ」でなく、追求や開拓、挑戦を待っている新しい何かが、そこにあること。
- 教室を率いる大村自身が、取り組みに本気の興味を持ち、知りたがり、楽しみに見守っていたこと。単なる点検者、評価者ではなかったこと。
こうした言葉も参考にしながら、書くことにおける「真正な場」が成立する条件について、考えていきたい。
[ad#ad_inside]