生徒が国語の授業の外で書いてきた文章を読むのは、どんなものだって楽しい。
学年で作っている文集。大学入試対策の小論文。自己推薦状。本当にごくごく稀にだけど、自分が書いたエッセイや小説を見せてくれる生徒もいる。そんな時はとびきり楽しい。
▼
どうしてこんなに楽しいんだろう。
点数をつける必要がないからだ。
▼
これは裏を返せば、「点数をつける」ということが、「文章を書く(表現をする)ー 読む(表現を受け止める)」という関係にマイナスに影響しているという僕の実感でもある。点数をつける以上、僕は「判定者」になって、満点の子とそうでない生徒を生み出す。そして満点ではない生徒に対するコメントは、「なぜあなたの文章は満点でないのか」という「理由説明」の部分を含まざるを得ない。それは、どうしたって前向きな文章にはならない。読む生徒の側も、点数がつけられるとその点数自体に意識が向かってしまい、コメントを「○○点の理由」として「処理」してしまって終わり、となるケースも多い。
▼
昨日、ある生徒が個人的に見せてくれた詩歌の鑑賞文を読んだ。丁寧に作品を読み解いているのに、論理が前面に出過ぎず、叙情的な文体で、その作品の魅力が、彼の言葉を介して浮かび上がってくる。息をのむ。まだ高校生なのに、自分のスタイルを作りつつある文章だ。
▼
読みながら、ファンになってしまう。自分の好きな詩を思い浮かべながら、あの詩をこの子だったらどう読むかな、話を聞いてみたいなと思う。こういう時に、「君の鑑賞文はこことここが非常によく書けていた、だから何点」や「論理性は4、表現は5…」などと言うことに、どんな意味があるんだろう。読んだ時の自分の気持ちを伝えて「今後も書き続けて、よかったらぜひまた読ませて」くらいしか言うことがない。言えることがない。
▼
彼の文章を読みながら、「文章を読む ー 書く」という関係の原点は、やはり「点数をつける ー つけられる」ではないと改めて感じる。それは彼のような文章上手の生徒でなくたって同じ。読んで、感想を伝えて、分からないところを質問して、相手の聞きたいことに答えて、提案して、励まして、また次を読ませてと伝える。読む人と書く人の関係性はそういう風に構築されるものなのに、点数をつけることは、その関係性をあっけなく壊して、別のものにしてしまう。
▼
誰が、点数をつけることを考えながら、あるいはルーブリック(評価基準表)を片手にしながら、他の人の文章を —小説や評論やエッセイや詩歌を— 読むだろう。そんな読者は実際にはいない。教員だけが、「教育」の論理でそれをやっている。自分もやっている。でもそれって、もしかしてとても不自然なことなんじゃないか。彼の文章を読みながら、そんな思いが強くなってくる。
[ad#ad_inside]

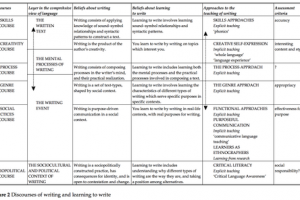


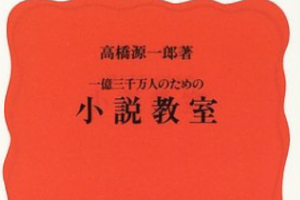

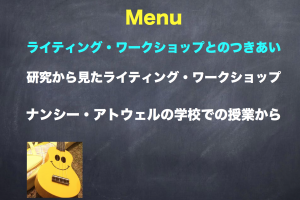


![[読書]そのまま使えて教室を変える、良い意味でのノウハウ本。ダン・ロスティン、ルール・サンタナ「たった一つを変えるだけ クラスも教師も自立する『質問づくり』」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/05/Screen-Shot-2016-05-28-at-22.36.51-50x50.png)

