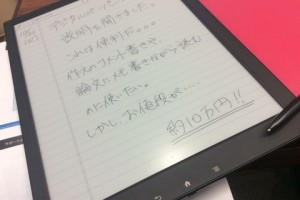先週末、長野県上田市で開催された「大村はま記念国語教育の会」に参加してきました。本当は長野県の中高の国語教育の実践家とつながりを作りたかったのですが、その目的はあまり果たせず…。ただ、大村はまの直接の教え子であり、大村はまについて様々に語り継いでいる苅谷夏子さんの話の中で、久しぶりに大村はま「優劣のかなたに」に再会しました。今日のエントリはその詩について。
[ad#ad_inside]大村はま「優劣のかなたに」
優か劣か
そんなことが話題になる、
そんなすきまのない
つきつめた姿。
持てるものを
持たせられたものを
出し切っている
生かし切っている
そんな姿こそ。
優か劣か、
自分はいわゆるできる子なのか
いわゆるできない子なのか、
そんなことを
教師も子どもも
しばし忘れて、
学びひたり
教えひたっている、
そんな世界を
見つめてきた。
学びひたり
教えひたっている
それは優劣のかなた。
ほんとうに持っているもの
授かっているものを出し切って、
打ち込んで学びひたり
教えひたっている
そういう世界。
優劣を論じあい
気にしあう世界ではない。
今はできるできないを
気にしすぎて、
持っているもの
授かっているものを
出し切れていないのではないか。
成績をつけなければ、
合格者をきめなければ、
それはそうなのだ。
今の日本では
教師も子どもも
力のかぎりやっていないのだ
やらせていないのだ。
優劣のなかで
教師も子どもも
あえいでいる。
学びひたり
教えひたろう
優劣のかなたで。
「優劣はある」ことを前提に
どうしたらこの「優劣のかなた」に行けるのか。それは、今の関心事の一つです。
素質や環境の差がある以上、学習に関する能力の優劣は確実にある。それは大前提だと思います。去年までの僕はものすごく優秀な生徒達を相手に教えてきたわけですが、彼らの学習意欲や理解力、そして長時間学習への耐性はとても高い。どの子にも最適な学習環境を用意すれば、彼らと他の子たちの学力差が拡大するのは必然だと思っています。かといって、「上を抑えることで学力格差を顕在化させない」ことに意味は感じられない。そういう扱いを受けた学力の高い子は、(典型的には受験をすることで)所属する集団を変え、学力が高い子だけのコミュニティを作り、結果としてコミュニティが分断されるだけでしょう。同様に、学習能力の相対的に低い子が置き去りにされることも認められない。どの子にも、学力の高い子も低い子にも、持っているもの、授かっているものを出し切ってほしい。大村はまがこの詩で書いたその願いこそ、「学びの個別化」の精神です。
どうやって「優劣のかなた」へ?
しかし、同年齢教室の中でこの優劣を意識する機会が積み重なるごとに、「劣」の立場に置かれる子(どんな場面でも同じ子が劣位に置かれることは非常によくあることです)の自尊心が傷つけられ、学習に向かうエネルギーが削がれるのも事実。「優劣のかなた」で「学びひたる」にはどうしたら良いのだろう….。
子ども同士がケアする文化をつくるアクティビティ
一つの答えは「子ども同士がお互いをケアしあう文化を構成的につくる」ことでしょう。軽井沢風越学園の岩瀬さんやKAIさんが公立小学校時代に、PAや構成的なアクティビティを通じてやっていたのは、このアプローチだったのだと思います。僕が毎週授業参観をしている片岡さんもこのアプローチです。それによって優劣の差のある子が分断していくのを防ぐ。有効なアプローチだと思います。
ただ、何度か書いていますが、PAについていうと、人間関係に介入すること(のみ)を目的としたアクティビティを、僕は生理的に好きになれないのですよね。僕が参加者としてこういう場にいることもとても苦手です。PAの効果がわからないわけではないけれど、こんな僕が仮にPAをとってもうまくいかないでしょうね。そこは僕の限界なんでしょうが、まあ、それでいいかな。子ども同士がお互いをケアする文化をつくるのだとしたら、国語の授業の中で、だと思っています。
大村はまとアトウェルの共通点
「優劣のかなた」に行くために、大村はまは何をしていたのでしょうか。面白いことに、彼女は構成的なグループ活動を通じて「子ども同士が支えあう文化を作る」ことには無関心だったように見えます。また、『学び合い』のように「みんな」を強調することもないし、「勉強のできる子ができない子を教えることで支え合う」スタイルにははっきりと否定的です。どうやら人間関係にアプローチする、という意識は彼女にはなかったようです。
彼女の場合は、基本的には、個別のカンファランスを通じて、教師が一人一人の子供に適切な教材と助言を与えることで、どの子も「優劣のかなた」に連れて行こうとしたのでしょう。よく大村は、一人一人の子供の顔を思い浮かべながら教材を作っていたと言います。たとえ学力の低い子でも、その子が夢中で取り組める教材や、皆の前で輝ける場面を学習活動の中で用意したわけです。
協働的な活動を通じた人間関係形成に関心がない、ということではナンシー・アトウェルも同じ。彼女もまた、大村と同様に教師と生徒の一対一のカンファランスを軸にして、どの子もよく学べる環境を用意しようとした。
要するに、教材の力を信じて、どの子も夢中になれる教材に出会いさえすれば、優劣の意識のかなたで夢中になって学ぶにちがいない。それが、大村はまやアトウェルのアプローチなのだと思います。
どんなアプローチを取るべき?
国語科教員の僕にとっては、もちろん大村やアトウェルのアプローチの方が断然魅力的です。ただ、大村やアトウェルのような実践をするには、一人一人の状態をきちんと把握して、膨大な教材の引き出しを持って…というスーパー超人でないといけません。僕の実力を鑑みるに、現実的にそれは難しそう。
また、大村がこのようなアプローチを取ったのは、あくまで彼女が生徒に最大週5時間しか会えない中学校国語科教員だったから、という事情もあったでしょう。もしも彼女が小学校教員だったら…もしも異年齢構成の学級だったら…違うアプローチを取っていたかもしれません。(と書きつつ、彼女は全くブレない気もしてきましたが….笑)
現実には、スーパー超人ではない僕は、子ども同士がケアしあう文化を、(願わくはPAのような活動ではなく)国語の力をつける活動を通じて作ることと、教師が適切な見取りをして個別の課題や助言を与えることの、どちらも中途半端にしかできず、中途半端を承知でその2つの組み合わせでやっていくのかなあ…という気がしています。
また、この件についてKAIさんに聞いた時に、「実際に優劣があることを、子どもがちゃんと分かっていることが大事」ということもおっしゃっていて、それもそうだなあと思いました。どうせ隠しおおせるものでもないし、「みんな同じ」と煙幕を貼っても仕方ない。少なくとも能力には優劣がある。それを事実として受け入れた上で、でもどの子にもいいところがあるよね、その人らしいところがあるよね、そう認め合える文化を、授業を通じてどうやって作って行くか。それが大事なのでしょう。言うは易し、行うは難し、だなあ…。
[ad#ad_inside]