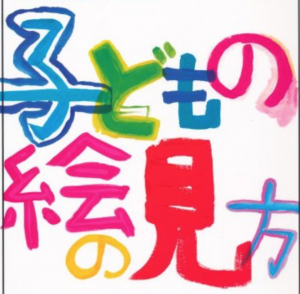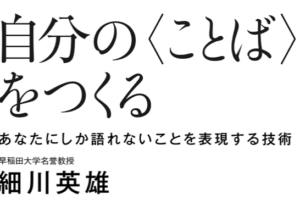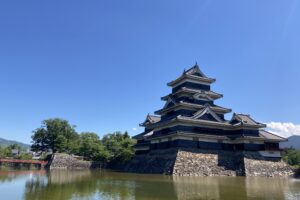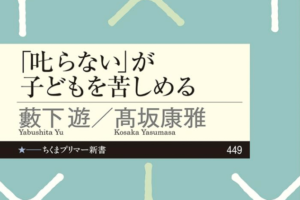対話型美術鑑賞の本『モナリザは怒っている!?』。2012年3月4日時点で、けっこう辛口のレビューを書いていて、いま新たに読み直すととても面白かったので、ここで転載したい。
2012年3月4日のレビュー
北海道の石川晋さんの授業を見学に行った際に、同席した中学校の美術教師の山崎正明さんに薦められたDVDブック。小学校での美術の対話型授業とその解説DVD、そしてその内容が活字になった本というセット。山崎さんへの興味で手にとった本。専門外の本ではあるのだけど、美術鑑賞と詩や小説の鑑賞はかなり似ているなあという発見があった。
ただ、正直に書くと、授業自体には全体としてあまりいい印象はなかった。僕が生徒だったらこの授業は何も教えてもらえなくてつまらないと感じただろう。「授業の導入部だけで終わっているような授業」とでも言えばいいのか、絵画を見て生徒が感想を交流させて、それで終わっているのだ。今回は(レビューらしくはないけれど)この授業について感じた違和感をもとに、僕の考える授業観も交えながら書いていきたい。
この授業では、小学校5年生が橋本周延「真美人 十四」(1897年)とジョヴァンニ・フランチェスコ・カロート「少年の肖像」(1520年)を読み、発見したことや感じたことを意見交流していく。担任の先生はそれを励ましながら意見をつなぐことに徹するファシリテーター役。生徒の発言はとても活発で、そこに先生の手腕がいかんなく発揮されている。だから、もしこの授業が、これから何時間か続く絵画読解の導入部の授業なのだとすれば、とても良い授業だと思う。
しかし、(授業全体の目標が示されていないので想像になるけれど)この授業はおそらくそうでない。だから、とても肝心なことが抜け落ちている。それは、子供たちが自分の絵の見方を、何かほかの視点によって相対化するという点だ。
この授業で、子供たちは基本的に自分たちの感じたままを述べていく。自分たちの時代感覚をもとに、過去の絵を意味づけていく。その時に表れる子供の絵の見方のクセ(部分から見る、とか、自分の関心に引きつけてみる)については、なかなか面白い。授業をする側にもこういう意識があると、意見交流を活発にする上で良いだろうと思う。
しかし、こうした子供の「読解」行為が、それを解説する大人によって、「自分の頭で考えている」とか「本質を見ている」とか肯定的に意味づけられるに至ると、ちょっと待ってよと思ってしまう。
これ、別に何も考えてないよ。子供はただ自分の感覚を肯定しているだけ。子供の絵の見方に大人がはっとするのは、ただ子供が大人の絵の見方に習熟しておらず、そのことが大人にとって新鮮だから。それだけのことじゃない? ちょうど国語教師にも、日本語の運用や語彙に習熟していない子供の書いた詩に過剰な詩性を読みとってしまう人がいるけど、それに対するのと似た違和感を抱いた。
こうした子供の感覚は、子供たちが大人世界にとっての他者であるから新鮮なだけで、別に子供たちが何らかの「能力」を獲得したゆえではない。現に、こうした面白い見方をする子供の大部分は大人になればごくふつうの見方をするつまらない大人になっていく。でもそれは、(例えば学校教育のせいで)子供が何かを失ったせいではない。自分の感覚を無自覚に肯定する子供が、そのままそういう大人になっただけの話である。
このDVDの子供たちは、最初から最後まで自分の感覚中心に絵画を見ている。その中には調べればわかることもたくさんあるのに、調べようとしない(先生も調べさせようとしない)。自分が無知であるという自覚もない。同時代の同地域の同学年というきわめて均質化された等空間の中で、ただ自分の感想を友達と交換しあっているだけ。
これで、絵画と「対話」していると言えるのだろうか?僕にはそうは思えない。ここが、僕がこのDVDの授業が好きになれない最大の理由。
絵画には、それが描かれた時代の感性や、その画家の個性や、それが鑑賞されてきた歴史など、様々な文脈がある。相手の持つそういう文脈を知ろうとしないで、「対話」といえるだろうか。このDVDは、絵画を使って自分自身と(あるいは自分と似た友達と)自己肯定の対話をしてるだけで、決して絵画そのものとは対話していないように見える。
たとえば国語の小説や詩の読解で、自分の感覚だけにもとづいてそれを読解する人がいる。まあ、そういう読みもありなのだが、それは決して豊かな読みではない。たとえば森鴎外『舞姫』を、現代的な恋愛感覚だけで読み解いて批評したら、それは単に『舞姫』を肴に自分の感覚を肯定してるだけで、決して他者としての作品に出会ったことにはならないだろう。自分の読みがどこから生まれてきて、それがその作品をめぐる様々な文脈の中でどのように位置づけられるのか、そして、自分には想像できないどんな読みがほかに存在するのか、そういう「自分の感覚をいったんカッコに入れて見つめ直す」経験を伴わない限り、作品と出会うことは決してできない。
これは、別に国語や美術に限った話ではないと思う。
自分、あるいは自分の生きる時代の感覚というのは、とても偏っていて、しかも自分自身ではそのことに気づかない。信じられないことが常識になっている時代/地域があったり、想像を超えたものの見方をする人がいたりする。勉強をする意味って、机の上でもいいから、自分の見方をいったんカッコに入れて、「理解不能なもの」「自分のものの見方を肯定してくれないもの」に多く出会い、未知なるものへの敬意(少なくとも「自分にはわからないから」という理由で断罪しない態度)を持つことにあるんじゃないか。自分の感覚や思考の限界を自覚して、それを広げるためのきっかけを与えるのが学校という場所。僕はそう思っている。
この本の著者(DVDの解説者)の上野さんは「書物や知識に頼るのではなく、自分の目と心と頭脳を駆使して」読み解く生徒たちを、まるでそれが良いことのようにほめていたけれど、僕は全然そうは思わない。「自分の目と心と頭脳」がいかにちっぽけで、偏っていて、しかもその事実に自分自身では気づけないか。そして、それを少しでも広げていくために「書物や知識」に代表される人間のこれまでの営みの蓄積が、どれほど有効か。教師が伝えるべきは、そこなんじゃないの。導入として子供の主体的な読みから始めるのは、子供の関心を惹く上でとてもいいと思うけど、ゴールがそこじゃまずいよ。
ちなみに美術鑑賞で言うと、僕はそんなに美術館が好きな子供ではなかった。好きな絵はあったけどその幅は狭く、自分の理解できない絵には「きっと世間の人も、○○の絵だからいいと言ってるだけだろう」レベル。しかし、大人になってから読んだ三浦篤『まなざしのレッスン』がとても面白くて、あれを片手に妻とイタリアの美術館めぐりをしたことで、僕の美術鑑賞への態度はだいぶ変わったと思う。『まなざしのレッスン』はまさに「絵を見るための知識」を与えるための本なのだけど、この本のおかげで絵を見るのがとても面白くなった。ある程度知識を持って見ると、その時代背景もわかるし、画家ごとの個性の違いにも目がとまるようになる。自分の好みも明確に意識されてくる。知識は決して感性を殺しはしないよ。知識があるからこそ、自分にとって未知な感性と出会えるのだから。
たとえば、親子で一緒に美術館に行く。好みをベースにした意見交流が一段落した後で、「今の○○にはまだわからないだろうけど、この絵はこういうふうに語られてきたんだよ」「○○が好きじゃないといったこの絵のここには、こういう意味があると言われているよ。こういうふうに評価する人もいるんだね。どう思う?」「この絵はとても変だろう?こういう絵が書かれるようになったのはね・・・」ということを伝えられたらいいなあと思う。
子供は、わかったようなわからないような顔で聞く。それでいいと思う。「自分にはわからないことがたくさんあるなあ」「自分とは違う見方をする人がたくさんいるんだなあ」ということを自覚させるだけでも、大人の役割は充分果たしたようなものなんだから。
2019年5月9日のコメント
著者の上野行一さんは『風神雷神はなぜ笑っているのか』の、奥村高明さんは『子どもの絵の見方』の著者でもある。面白いことに、この2冊の著書については僕は好意的なレビューを書いているのだ。