ノルウェー隊のアムンゼンとイギリス隊のスコット。南極大陸探検の物語というと、僕にはこの偉大な二人のライバル物語が頭に浮かぶ。でも、南極大陸には彼ら同様に強烈な印象を残す「偉大な失敗の記録」があった。それが、本書の主人公アーネスト・シャクルトンと、彼の指揮下にあったエンデュアランス号乗組員26名の、遭難と生還をめぐる物語である。ある人の薦めで読んだのだが、面白かった!
[ad#ad_inside]帝国南極横断探検隊の漂流記
この本は、1911年のアムンゼンの南極点到達を受け、1914年に南極大陸の横断に挑んだイギリスの帝国南極横断探検隊の漂流記だ。アーネスト・シャクルトンを隊長とする探検隊は、帆船エンデュアランス号に乗って南極大陸の横断を目指す。しかし、早々に海氷に囲まれてしまう。それでも氷の間を縫うように進んでいったが、1915年の1月には、エンデュアランス号はついに身動きがとれなくなってしまったのだ。
こうして、彼らの苦難の漂流がはじまる。その後も海氷に翻弄され続けた彼らは、11月にはエンデュアランス号を捨ててキャンプを設営し、マイナス30度の酷寒の地でのサバイバルを覚悟しなくてはならなくなる。
この本では、過酷な状況の中でシャクルトンがどうやって仲間たちをひっぱり、生き延びていったかが描かれている。何よりも印象深いのは、シャクルトンが常に仲間をはげまし、前向きな姿勢を崩さなかったこと。低い生存可能性に賭けながらも、誰一人見捨てず、全員で帰るのだという意思を持ち続けていたことである。加えて、たとえば気がふさぎがちなメンバーは自分と同じテントにするなど、メンバーの性格を見ての配慮も怠らなかった。シャクルトンと同じ場にいると、気がふさぎがちなものも明るくなるからだ。周りからは気づかれないように、常に配慮を怠らなかったのである。月並みな言葉だけど、強力で頼りがいのあるリーダーだったのだろう。
キャンプ生活のはてにエレファント島にたどりついたシャクルトンは、仲間たちを救う唯一の方法として、6人のメンバーで小さなボートケアード号に乗って、遠くはなれたサウスジョージア島に救援を求めに行く。そして、踏破不能と思われていた山脈を超え、無事に町までたどりつくのだ。その後は何度も救援要請を繰り返し、最終的に1916年8月、エレファント島に残した仲間全員の救出に成功したのである。
副隊長ワイルドの奮闘
この本の中では、シャクルトン以外にも何人かの船乗りが描かれている。天才的な操船技術を持つ船長のワースリー。出航直前のエンデュアランス号に無断で乗り込んできた19歳のブラックボロ。すぐれた船大工だが人付き合いが悪かったハリー・マクニーシュ。このような多士済々をシャクルトンはまとめあげていた。
中でも、強く印象に残った人物がいる。それは、漂流生活の後半に、サウスジョージア島に救援を求めに船出した隊長シャクルトンと離れて、エレファント島に残る21人の仲間たちを統率することになった副隊長のフランク・ワイルドだ。彼はもともとシャクルトンのような明るい性格の持ち主だったようだが、エレファント島に残ってからはいっそう彼にならって前向きな姿勢を見せ続け、「今日こそボスが迎えに来るぞ!」と隊員に声をかけつづけていたらしい。
順調なら1ヶ月もかからないはずが、実際にワイルドたちがシャクルトンに救援されるまでは4ヶ月半もすぎていた。おそらくワイルド自身も、シャクルトンの死と、自分たちに救援がないことを覚悟していただろう。それでもシャクルトンの代役を果たし続け、残った隊員に誰一人の死者も出さなかったワイルド。彼こそシャクルトン隊の生還ストーリーの最大の立役者ではないだろうか。
幸運と不運を招き寄せる不屈の男
常に明るさとユーモアを忘れず、希望を持って行動した不屈のリーダー、アーネスト・シャクルトン。探検隊27名全員の生還という奇跡的な出来事。強運の持ち主かと思いきや、探検隊以外の事業では失敗し続けるなど、幸運と不運をともに呼び寄せてしまう男という印象もあるのが面白い。
生還がわからない探検に何度も出かけ、国内にいたらいたで事業に失敗するシャクルトンを支える家族もさぞ大変だっただろうと思う。この本を読んだ僕の妻は「いちばんすごいのはシャクルトンの奥さん」と言っていたが、それも頷けるほど、妻のエミリーは忍耐し続けたんじゃないかな。夫よりも忍耐強いかも…。(ちなみにシャクルトンの死語に遺体をサウスジョージア島に埋めるよう希望したのも奥さん)
「どうしてやりとげることができたのか、わたしにはまったくわからない」
救援要請に行く途中にシャクルトンが敢行したサウスジョージア島の山越えについて、30年ほども後に「史上2番め」の山越えを達成した登山家が、次のように述べているそうだ。
彼らが、それをやらなければならなかったということはわかる。しかし、彼らがどうしてやりとげることができたのか、わたしにはまったくわからない。
これは、山越えだけでなくシャクルトンたちのサバイバル全てを象徴した賛辞だろう。海氷にはじまる多くの不運にさいなまれ、時々の決定的な幸運を味方にして、シャクルトンたちは生き残った。しかし、彼らがどうしてそれをやりとげることができたのか、それを納得できる形で説明するのは難しい。もちろんそこには、ユーモアや前向きさの持つ力や、シャクルトンやワイルドのリーダーとしての素晴らしさなど、いくつかの要因があるだろう。けれど、それだけではどうしても説明できない「何かの力」が、この時の彼らにはあったようにも感じる。彼らのなしたことは、それほど偉大なことだ。そのストーリーを思う存分楽しませてもらった。
[ad#ad_inside]


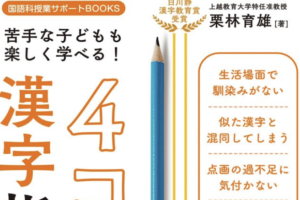





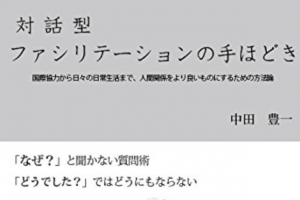

![[読書]価値観を揺さぶる迫力のある本。村上公也・赤木和重「キミヤーズの教材・教具」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2018/08/スクリーンショット-2018-08-18-19.03.02-50x50.png)