今日は前回のエントリ(下記参照)の続き。前回は「最近の自分、停滞期だなあ、飽きてるのかなあ」という自覚を深めて、その原因をさぐったまで。今日は、「では、その飽きからどう抜け出すのか?」を考えてみる。ちなみに、この時点で確たる答えは持っていないDiscovery Writingだ。書いた結果、どんなことが発見できるだろう?
観察力のある人は「飽きない」のか?
と書いていきなり自分以外の話なのだけど、ふと思ったこと。目の前の子供に興味があり、かつ観察力がある人は、毎日の学校での仕事に飽きないのだろうか? というのも、子どもは毎年変化するし、受け持ちの子も変化する。実践者がきちんと目の前の事象を観察していれば、日々は些細な変化にあふれている。「飽きない」を「常に新しい問いやテーマを見つける」と言い換えれば、目の前の事象に興味があって観察力があれば、常に新しい問いやテーマを見つけ、面白がれるので、「飽きない」「停滞しない」気がする。これ、自分はそういうタイプではないのでなんとも言えないんだけど、風越とかSNSとかで、「あの人は飽きなさそう」な感じの人はいる。どうなんだろう?
自分を飽きさせない2つの方法
でも、多くの人は「全く飽きない」ことは無理だろう。僕の場合、風越学園で56年を連続して受け持って4年目で、ライティング・ワークショップやリーディング・ワークショップは、同一教材を何度も使う授業ではないので比較的飽きにくいはずだが、それでもやっていることの新鮮味は徐々に乏しくなってしまう。多くの人は、同じ現場にいればいるほど「ルーティーン」が増えて、慣れて、飽きてきてしまう。そう考えると、公立学校で数年ごとに異動がある仕組みは、教育の公平性を担保する仕組みであると同時に、教師の「飽き」を回避する工夫なのかもしれない。(私立学校でも同じ理由で定期的に配置転換をする学校もあるだろう)
一方、長く同じ現場にいる私立学校勤務を前提としたら、自分自身で「飽き」を回避する技術や工夫が必要になってくる。例えば冒頭に書いた「観察力のある人」は、「同じ現場にいても、常に違うように見えているので飽きない」わけだ。同じ現場にいても、常に違ったように見える「見方」を持っていれば、飽きることはあまりない。だから観察力って大事だよね、と思う。(言い方を変えれば、「いまの見方」には比較的すぐに飽きているからこそ次の見方に移行するわけで、飽きない人とは常に小さく飽きている人だとも言えそうだ)
では、観察力に乏しい人、世界の見方を変えられない人は、どうやって「飽き」を回避するのだろう。見方が変わらないのであれば、自分で変化を起こすしかない。そういう人は、きっと、外からは一見同じことの繰り返しをしているように見えても、自分が飽きないように、常に新鮮な要素を自分の実践に取り入れるマイナーチェンジをしているはずだ。
宇野常寛『ひとりあそびの教科書』には、ゲームをやりこんでいくと、通常のやり方でクリアするのに飽きて、あえて自分に不利な制約(ルール)を課す「縛りプレイ」をはじめ、やがては自分ではプレイしないでコンピュータに任せる「委任プレイ」をはじめる、という話があった。これも、ルール・チェンジによって「飽き」を回避する方法だ。
実践をマイナーチェンジして「飽き」を回避しようとする心理は、とてもよくわかる。どんな遊びも、それをやり尽くして飽きてくると、ルールを変えてみたくなるもの。そうか、考えてみたら僕の今年の「カンファランスをやめてみる」試みも「縛りプレイ」の一種だったんだな…(笑)
というわけで、同じ現場にいながら自分を飽きさせない方法には、①同じ現場でも、違うように見えるように、自分の見方を変える、②ゲームのルール(授業のやり方)をマイナーチェンジする、の2つがあることがわかった。この2つを意識して、自分が飽きないためのどんな工夫ができるかを考えてみたい。
教室を、「本を書くための場所」として見直す
同じ現場を自分の見方を変えて見てみる、というのはなかなか難しい。どういうレンズをかけて見たら目の前の教室が新鮮に違って見えるだろう…と思って考えてみたら、読み書き好きの自分の場合は、教室を「本のネタを集める場所」として再定義するのが一番良いような気がしてきた。『君の物語が君らしく』は結果として風越学園の教室が本を書くための材料になったのだけど、むしろ「本を書く」ことを前提にして、教室をそのネタの収集場所として眺めてみる、ということだ。ここまで書くと教育関係者としてはなんだか本末転倒すぎて罪悪感あるな…。
でも、自分の実践をもとに「次の本」のことを考えながら授業をするのは楽しそうだ。これまで、リーディング・ワークショップ(読書家の時間)寄りの関心では『中高生のための文章読本』を出版して、ライティング・ワークショップ(作家の時間)寄りの関心では『君の物語が君らしく』を書いたから、なんか別なのがいい。詩が好きだから、児童向けの詩の本とかいつか出してみたいな。そのための実践の場としても教室をとらえなおす。例えば、詩人の人に連続授業に来てもらって、僕も子どもたちと一緒に詩をつくって、それをもとに本にする。そういうビジョンをもって授業をしたらけっこう楽しいんじゃないだろうか。
授業のマイナーチェンジ…その方向性は?
飽きないための2つめの方法は、自分を飽きさせないために授業のマイナーチェンジをすることだった。これも有効な方法だ。ただ、実は僕はこれまでもそういうマイナーチェンジを繰り返している。今年だって、うまくいかなかったマイナーチェンジに「カンファランスをやめてみる」があったけど、うまくいったマイナーチェンジに「出版記念オーサーズトーク」や、教室に大人の書き手を招くことを増やしたのもあった。
というわけで考えてみると、この種のマイナーチェンジは風越にきてからずっとやっているので、単にマイナーチェンジをするだけでは、これまでと変わりなさそうだ。マイナーチェンジをする方向が大事なんだろうか。では、それはどんな方向なんだろう。こういう方向にマイナーチェンジをすると楽しそうな方向性って??
これまでのマイナーチェンジでいいなと自分でも思うのは、「ファンレターへの返信を書く」だったり、「出版記念オーサーズトーク」だったりする。どちらにも共通しているのは、「出版した作品やそれまでのプロセスを丁寧に扱うことで、書き手としての喜びやアイデンティを高める」ということ。別の視点から見たら、「書くという営みの楽しさを増すために、他者を介在させる」方法であるとも言える。
そして、実はこのどちらにも共通しているのが、「自分で考えたのではなく、他の人に教えてもらった実践」だったということ。「ファンレターへの返信」は、『読書家の時間』『社会科ワークショップ』の著者・冨田明広さん(トミー)に教えてもらい、「出版記念オーサーズ・トーク」は、風越同僚の片岡利允さん(とっくん)がやっているのを見て「いいな」と思ってアレンジしたものだ。やっぱり、自分ひとりで考えるんじゃなくて、誰かと一緒に考えるのも大事そう。この「誰か」は別に本の著者でもいいし、まあ、ざっくり言えばインプットしろってことだよね、たぶん。
そうだ、冬休み前に同僚の山﨑恭平さん(ざっきー)と国語の授業の振り返りをしていて出てきた授業の改善案に「『作家の時間』の毎回の最後のオーサーズ・トーク(共有の時間)のやり方を変えてみたらどうか?」という話があったな。「教室の中でライターズ・グループをつくれないか」「お互いがお互いの『信頼できる読み手』になるために、もっと時間を使えないか」という文脈での話だった。これなんかは、ざっきーと一緒に『自分の「声」で書く技術』を読んでライターズ・グループを実践してきたからこその話だった。このへんに焦点をあてて、自分の実践をマイナーチェンジしてみる、というのはありそう。三学期、さっそくやってみようかな。
今回の考察はひとまずこれまで。すんごい深い洞察とか革新的なアイディアが出てきたわけじゃないけど、それでもいったん自分の現状を「停滞」と認めた上で、いまの自分の興味を活かしたら「こんなことできそう」「こんなことやってみたい」と思えるのは、なんだか気分が明るくなるね。ひとまず三学期に試したい方向性が定まったし、これで少しは年を越せる気分になったので、まあよしとしよう!
[ad#ad_inside]






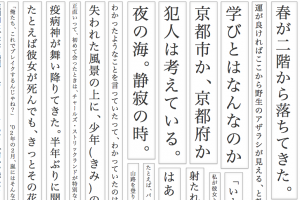




![[読書]教室に読者共同体を作るための具体的手立て。ジェラルド・ドーソン『読む文化をハックする』](https://askoma.info/wp-content/uploads/2021/02/260a394a2bdf3a75d43ebb5675d74d74-50x50.png)

