ライティング・ワークショップの授業は、いったん筆をとめて(ただし筆を使っている人はゼロ)下書きを読みあう「編集会議」の段階を終えました。これから推敲に入る人が多いかな。2作品目に行く人もいれば、まだ1作品めを書く途中で悩んでいる人もいます。書き手はそれぞれ。
ミニレッスン用に「会話」について書いた文章を何人かの生徒に褒めてもらえたので、調子に乗って、少し手直ししたものをアップします。ラーメン屋についてのエッセイの下書きも一緒に見せたんだけど、そっちよりも反応良かったな…。
ミニレッスン・「書かれた会話」の難しさ
「小説やエッセイの中で、自然な会話を書きたいって?それは難しいなあ」
「なぜなのかしら?」
「そもそも、実際に話されている会話と、小説やエッセイの中の書かれた会話は、全然違うんだよ。実際の会話を録音すると良くわかる。実際の会話は、とても短くて支離滅裂。話す途中で言いよどんだり、主語と述語が対応していなかったり、どもったり、同じことを反復したり、省略されたりが当たり前に起きる。話しているとちゅ」
「途中でさえぎられることもしょっちゅうあるわよ」
「……その通り。だから、書き言葉で現実の会話を再現すると、とても読みにくくなる。一方で、小説やエッセイでの会話は、現実の会話ではありえないくらいに整っていて、前後の文章の整合性が高いし、一文も長くなる傾向があるんだ。僕のこの台詞のようにね」
「なるほど。書かれた会話は話し言葉よりも書き言葉に近い、ということかしら」
「そうなんだ。ところが逆に、あまり書き言葉に近すぎても、話し言葉として不自然に感じられるのが、難しいところだね。例えば、さっきの『整合性』なんて言葉、話し言葉としては極めて硬い気がするだろ」
「そうね。その『極めて』っていうのも硬いわ」
「話し言葉には話し言葉らしい言葉の選び方がある。そこに気を付けないと、小説やエッセイの中での話し言葉が、会話として不自然になっていくんだ」
「なるほど。他にも、書かれた会話の特徴はあるの?」
「あるよ。例えば僕たちの話し方だよ」
「えっ、私たちの?」
「ここまで読んできて、読み手は、僕が男で、君が女なんじゃないかって思っているはずだ」
「口調からするとそうよね」
ニヤリと笑うと、ゲイバーで働いている益男さんは、だまされちゃうのよね、とつぶやいた。
「語尾に『わ』とか『わよ』なんてつける女性は、実際にはあまりいないのにねえ」
「そう。書かれた会話には、そういう『書き言葉の中で典型的に使われる話し方』が出てくる。役割語ともいうらしい。女性が語尾に『~だわ』『~わよ』を使ったり、年老いた博士が『~じゃ』『~だわい』を使ったりするのがそれだね」
「マンガやアニメにもよくあるわね」
「フィクションの特徴だね。こういう役割語は、性別・年齢・地位・出身地などの個性を反映するから、読み手が発話者の人物像を推測する手がかりになるし、いま誰が話しているのかもわかりやすい」
「だったら、どんどん使えっていうこと?」
「でも、こういうのって、現実とは一致しないステレオタイプだ。だから、役割語を使いすぎると、デフォルメしすぎた幼稚な印象になってしまう。ライトノベルみたいに、特徴的な言葉づかいでキャラクターの個性を会話で際立たせる小説もあるんだけどね」
「難しいわね……。他にも注意すべきことはあるかしら」
「会話は地の文と組み合わせて使うっていうのは、知っておいていいかもね」
「なにそれ」
「会話は普通、僕たちの会話みたいに進んでいくだろ」
「なるほど、カギカッコでくくって話していくというわけね」
「そう。ただ、カギカッコがずっと続くのも単調になるから」と、僕はこの文章の作者のほうを見てから、
「たいていは、地の文と組みあわせて書く」。こんなふうにね、と、肩をすくめてみせた。
会話について解説するためのこの会話に、僕はいいかげん飽きてきていた。早く終わらないのかな。でも、益男さんは「これも仕事よ」と目で合図して続ける。
「地の文にはどんなことを書くといいの」
「候補としては三つあるね。一つは、誰が発話したか」と、僕は言った。
「今みたいなやつね。でも、こればっかりだと単調ね。二つ目は?」と、益男さん。
「それから、どんなふうに発話したかだ」僕はうんざりした口調で答えた。
「今の『うんざり』ね。三つ目は?」その声も、どこか同情めいて響く。
「何を発話したか、だよ」最後にそう解説を加えた。それから僕は、別に会話の内容を地の文で書いてもかまわないということを強調した。そして、会話を書くのはとても難しいけれど、地の文と組みあわせれば、極端に単調になることは避けられるはずだ、とも。
僕たちの会話はそこで途切れ、少しの沈黙があった。どこからか、授業終了のチャイムが聞こえてくる。
「もう、いいよね」
「ありがとう」益男さんは、笑顔を見せた。「エッセイを書こうとしてて会話の場面に困ってたんだけど、これでなんとかなる気がする」そう言って帰りかけた益男さんは、ドアを開けた時に、何かを思い出したらしい。
「そうだ、釘を刺しておくけど」ふりむいて軽く僕をにらんだ。
「ゲイバーで働くキャラクターが『だわ』と話すのだって、立派なステレオタイプ、偏見なんだ。これからは注意するんだな」
ぴしゃりとドアを閉めた益男さんを追うこともできず、僕は一人で立ち尽くすしかなかった。
[ad#ad_inside]

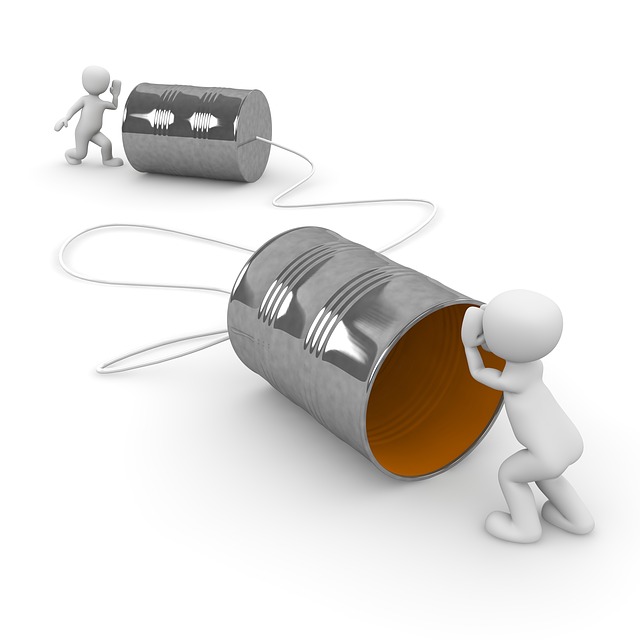









![[読書]気づけば山の本ばかり。単独行をめぐっての2023年7月の読書。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2020/02/book-2388213_1920-50x50.jpg)