2月に読んで下記エントリで触れた山元隆春「読者反応を核とした『読解力』育成の足場づくり」。
目次
読者反応理論の理論と実践
この本の特徴は、前半(第一章)で、1980年代から90年代にかけて国語教育の基礎論として議論された「読者反応理論(reader- response-theories)」の展開についてまとめられていることだ。第二章以降は、そういう理論的展開を受けての実践例になる。後半も絵本の読み聞かせの実践やグラフィック・ノベルの利用など面白い事例が並ぶのだけど、僕にとっては前半が特に勉強になったので、そちらを中心にメモしたい。
読者反応理論とは?
「読者反応理論」(ないし読者論)というと、読むことを読者と作品の相互作用と捉えるヴォルフガング・イーザーの読書行為論や、読者と作品と状況の三者の交流とするルイーズ・ローゼンブラッドの交流(transactions)という概念がよく知られている。いずれも一人一人の読者が、テクストに反応することで「意味」が生成されるという、読者の役割を重視する理論である。
アンチ・正解到達主義として
ここからは僕の浅薄な理解によるまとめになってしまうけど、日本の国語教育では、1980年代から90年代にかけて、この読者反応理論が広まっていった。70年代までは「正解到達主義」の教え方、つまり、国語教師が(ないしはその背後にある学問的な権威が)、テクストの読み方の「正解」を決め、授業で生徒にそこに到達させようとする教え方が中心だったのが、80年代以降は、正解到達主義へのアンチテーゼとして読者反応理論が受容され、広まっていった。今では程度の差はあれ、読者反応理論の基本的姿勢は、国語教育現場でも広く受け入れられているように感じる。「唯一正しい読みに到達するのが読みの授業だ」なんて考える国語教師は、いても少数派なのではないだろうか。
みんな違ってみんないい?
ところが、読者反応理論をベースにした授業にも、よく知られた危険がある。それは、「正解到達主義」を否定して読者が「意味」を生成する役割を重視するあまりに、「読者が生成した意味ならなんでもあり」「みんな違ってみんないい」になってしまうことだ。これは、日本では田中実さんや須貝千里さんらが「読みのアナーキー」として、長年批判してきた問題である。
読者反応理論に依拠しつつ、読解力を育成する
この本では、同じような問題意識を共有しつつ、「読者反応理論」のアメリカでのその後の展開が説明されている。「読者各自の「思い」をかたちにして出し合うだけの、何者ともかかわろうとしない読みを生み出してしまう」(p19-30)という、読者反応理論をベースにした授業が持つ危険に対して、様々な活動を通じて、「社会的に構築され、文化に埋め込まれた個人としての一人ひとりの読者」としての読解力の育成にどのように働きかけるか、が論じられている。読者反応理論に依拠しつつ、個人の感想に閉じないで読解力を育成するにはどうしたらいいのか。それが本書のテーマなのだ。
「喜びを味わう」読みと「情報を取り出す」読みの往還
まず僕が勉強になったのは、ルイーズ・ローゼンブラットの交流理論について。ローゼンブラッドの理論というと、読者が文章を読むときの姿勢を「喜びを味わう」(aestheticな)読みと、「情報を取り出す」(efferentな)読みの二つに分けて、主に小説を読むときに使われる前者の読みのスタンスを重視していた印象を持っていた。でも、この本を読んで、その印象が僕の不勉強による誤った理解だったことがわかった。
山元さんによると、ローゼンブラットは、「読む」という経験が、「喜びを味わう」要素と「情報を取り出す」要素の連続体の上に成り立つ、ということを終始強調している。重視するスタンスの差こそあれ、どの文章のジャンルにも、そのいずれの要素も存在する。例えば、説明的文章を読むときには「情報を取り出す」読み方で読み、小説を読む時には「喜びを味わう」読み方で読む、ということは、彼女は一切言っていないのだそうだ。
そうではなくて、「読むこと」の能力を育てていくためには、「喜びを味わう」スタンスと「情報を取り出す」スタンスを絶え間なく往復することが重要であるとローゼンブラットは言っているのです。…そのように捉えたとき、交流理論は大切なことを見極める「批判的読み」を基礎づける理論となります。(p57)
なるほど、ローゼンブラットの主張をこのように理解すれば、読者反応理論の立場をとったからといって、それが即「一人ひとりの読みが正しい」ということにはならない。本書で紹介されているミンシュイ・カイの議論のように、「喜びを味わう読み」は、「絶え間ない自己発見を導く批判的読みの基盤」(p59)にもなりうるのである。
「生きた回路」を育む
また、ローゼンブラットは、読者は作者の言葉や考えに単に同化するのではなく、作者の言葉に反応しながら、知的にも感情的にもその世界について理解したことを使っている、と述べ、そのプロセスを「生きた回路(a live circuirt)」と読んでいる。山元さんが重視するのは、この「生きた回路」を育むことだ。そこが、「何者ともかかわろうとしない読み」から抜け出し、他者に読みを開く上で大事だからである。
そのために山元さんが参照しているのが、ダグラス・ヴァイポンドとラッセル・ハントの読みの研究である。ヴァイポンドとハントは、読みの形式を「情報駆動の読み」(学んだり情報を取り出したりするための読み)、「物語内容駆動の読み」(物語世界の中を生きるための読み)、「要点駆動の読み」(物語の要点や物語の存在理由など、物語の語り手のプランを評価する読み)の三つに分けているが、山元さんは、この「要点駆動の読み」こそが、「生きた回路」を成り立たせるためには重要なのだという。
「要点駆動の読み」とは何か?
「要点駆動の読み」とは、他者の話に耳を傾ける聞き手が「この人はこの話で何を伝えようとしているんだろう?」と話の「要点」や、そこにこめられた話し手の意図を考えながら聞くように、「目的をそなえたコミュニケーション行為の産物として作品を理解する」(p68)姿勢のことを指す。物語を語り手と自分のコミュニケーションと捉えて、「この話はどういうこと?」「ここでどうしてこの表現を使っているの?」というふうに、「要点」をつかまえて、物語の語り手の意図を共有しようとする読みだ。
要点駆動の読みをする時、読み手は作品に対して様々な「評価」を行う。物語中で使われる比喩や表現について、物語中の登場人物や設定について、そして物語における語り手の語り方について。だから、要点駆動の読みとは、こうした「評価構造」で成り立つ読みでもある。山元さんは、こうした読みこそが、作者と読者の間の「生きた回路」を成り立たせるのだ、と言う。
「要点駆動の読み」において読者が用いる方法
「生きた回路」を成り立たせる「要点駆動の読み」において、読者は具体的に何をするのだろう。山元さんは、それを3つの方法に分類している。
一つは「結束性を求めて読む方法」。作品全体を作者が何からの動機のもとに構築したものとして捉え、あらゆる証拠が揃うまで個々の要素への評価を差し控えつつ、その結束性を作り出そうとする方法。二つ目は、「物語の表層に注目する方法」。視点、トーン、文体、語法と行った個々の局面に注目しながら、「標準的ではない要素」に注目して、そこに作者の何らかの目的に基づいた仕掛けがあるだろうと捉える方法。そして三つ目が、「作品を、作者・語り手・登場人物の間のやりとりとして読む方法」。ここでは、読者は、作品に内包された作者や語り手の価値観及び新年と、登場人物の価値観および信念を安易に同一視せず、むしろその間の矛盾に目を向けようとする。
こうした3つの方法を用いて読者が要点駆動の読みをする時、読者と作者の間に「生きた回路」が生まれ、読者は「自分ひとりの読みが正しい」という隘路から抜け出すことができる。
「読者反応理論」の立場から、「作者」を扱う
この三つの方法は、ざっくりまとめれば「全体の構造」「細部の表現」「語り手」にそれぞれ注意を向ける方法であるとも言える。したがって、「要点駆動の読み」も、こうした個々の方法に分解してしまえば、一定の知識と経験のある国語教師にとっては、それ自体では何ら目新しいことではない。自分の授業でもそんなこと教えてるよ、という人も少なくないはずだ。
山元さんの論の価値は、こうした「作者」の工夫に関わる要素を「読者反応理論」を支えるピースとして再配置したことにあるだろう。読者反応理論の立場に立ちつつも、「私がそう読んだのだからそれが正しい」という「読みのアナーキー」に陥らず、作者や語り手の存在を措定して、読む力を育てるための論の展開を、山元さんは用意したのである。
こうした視点のもとに、第二章以降では、様々な具体的な実践が紹介され、論じられていく。読解力を育成する教材としての「絵本」の読み聞かせ、「テラビシアにかける橋」を用いた8週間のブッククラブ実践、シェリダン・ブラウの「文学ワークショップ」実践などが紹介されているので、興味のある方はぜひ読んでみてほしい。
個別自由読書だけでは「足りない」理由
個人的には、この本は去年から抱いていた「個別自由読書だけで読解力は育つのか?」という疑問、つまり、多読をすればそれで十分なのか、違うのではないか、という思いに答えの方向性を与えてくれた本でもある。個別自由読書を推進するアトウェルは「リーディング・ゾーン」に入ることを何より重視し、ローゼンブラットの論もそれを支えるために引用しているけれど、「リーディング・ゾーンに入って夢中になって読む」だけでは「要点駆動の読み」は発動しにくい。そこに、他者に開かれる回路がないといけない。
おそらく、アトウェルの授業では、最初に全員で行う「詩をひらく」(umpacking a poem)ことや、ミニ・レッスン、そしてレター・エッセイを書く営みが、「要点駆動の読み」を発動させる仕掛けとして機能しているのだろう。それなしでの個別自由読書だけをしても、読解力は高まらないのではないか。
同時に、アトウェルの授業で「要点駆動の読み」を成立させているのは、ライティング・ワークショップなのだろう。書く立場に身を置くことで、書き手は、作家の立場で作品を読むようになる。作者が使っている技術や、その裏側にある意図にも気を配るようになる。読者が書くことが、読者と作者の間の「生きた回路」を成立させるのだ。これは、僕自身がライティング・ワークショップをやっていても感じることでもある。書くことを通じて、生徒たちは読むときの視点も身につけている。
もちろん、個別自由読書は必要だ。個別自由読書は、各自のレベルに合わせて語彙を増やし、読書の流暢さやスタミナを養う。けれど、読解力を育てるためには、個別自由読書と同時に「要点駆動の読み」を成立させるための仕掛けも必要なのである。この本は、そう思わせてくれた本だった。読んで良かった。おすすめです!



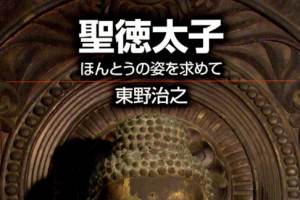





![[読書]インドの古典「ヒトーパデーシャ」が抜群に面白い!2018年8月の読書。](https://askoma.info/wp-content/uploads/2018/08/キャプチャ-50x50.png)


詳しいことはよくわかりませんが、読んでみた印象としては、
「要点駆動の読み」や「生きた回路」を活性化させる指導が、わりと今までの国語教育の授業でもなされてきてたのかな?と思いました。
また、国語の時間でやっているような設問にあっちこっちをみながら自分なりに「答え」を見出そうとする読みをすることも、実際の読書活動の中ではほとんどないようにも思います。たとえば、同じ本を読んで同じ疑問を考えている状況も珍しいでしょうし。そう考えると、意外と貴重な時間?だったなと思いました。
本はひとりで読まずに他の人と一緒に読みたいものだとも。このブログもそういう意味でありがたいです。感謝。
ちなみに山元さんは私の大学時代の先輩で、とても優しいいい方です(笑)