以前に下記エントリで書いた通り、昨年読んでとても面白かった本を自分のためにまとめておく。この本、基本的にはスポーツのような「身体を使った学習」についての本だけど、考えてみると「教える」って、周囲の環境の中で自分の体感を頼りに学ぶ「身体知」的な側面が大きいのだ。そういう立場にいる僕にとって、とても勉強になって、勇気をもって踏み出すことを助けてくれる本でした。
目次
What研究とHow研究の関係
まず面白かったのは、What研究とHow研究の話。例えば、上手なプレイヤーを分析して、初心者と何が違うかという研究(エキスパート・ノーヴィス・ディファレンスの研究)は数多いが、こうした「What(何が違うか)の研究」だけでは、初心者の熟達は助けられない。というのも、上手なプレイヤーの動きに近づくには、本人がどういう意識をもち、自分の身体を使ってどう実践するかがわからないといけないからだ。そういう身体知の学びを進めるためには、「どう実践するか」についての「Howの研究」が大切だという。これは、大事なことだと思った。人は機械ではないものね。どうやって熟達するかは、本人なりのやり方が大きいのだ。
言葉と身体知の関係
そして、その「Howの研究」において大切な役割を果たすのが言葉なのだという。言葉と身体知の獲得についての筆者の説明は、次のようなものだ。
まず、暗黙性が高いものごとを言葉にする意識を持つことで、自分の身体や周囲の環境についての着眼点が増える。例えば、「肩甲骨」という言葉を持つことで、「なるほど、肩甲骨の距離が近いのが、胸を張るということなのか」というふうに。こうして着眼点が増えていけば、着眼点同士の関係性にも問題意識が向くようになり、熟達のための自分なりの問いが立つ。この問いに向き合うことで、自分の身体の動かし方が徐々に変容し、それをまた言葉にすることで、体感の類似性や連動性にも気づくようになる。こんなふうに、「言葉」と「体感」は連動しながらどんどん増えていく。
(第5章のざっくり要約)
筆者はこういう風に、熟達の過程を、周囲の環境の中で身体が振る舞う時の体感のネットワークの形成と捉え、これを「身体-環境モデル」と呼んでいる。この、「言葉にすることで着眼点が増える」という話は、岡田暁生さんの「音楽の聴き方」でも出てきた話だった。音楽も身体知だから当然とも言えるが、感覚的なものごとを言葉にすることで意識化でき、熟達する、ということなのだろう。
「こつ」を生み出す必要悪としての「スランプ」
こうしたモデルの具体例としてあげられているボーリングスコアの研究が面白い。ボーリングの練習をしつつ、その時の体感をずっと記録にとっていたところ、「身体の詳細な動きや部位についての言葉が増えている時には、ボーリングのスコアが悪く、言葉の量が減り、また大雑把な全体の動きを捉えている時には、スコアが良い」という結果が得られたそうである。あれ、熟達に言葉が必要なのではなかったの? 言葉が増えると下手になる? なぜそういうことが起きるのだろう?
筆者はこの現象を「必要悪としてのスランプ」として説明する。身体の詳細な部位や動きについての言葉が増えるとは、「着眼点」が増えていく状態だ。これは、自分の身体と環境の関係を言葉で構築する時期に相当する。この時期、プレイヤーは多くの着眼点を意識して試行錯誤するので、その過程で不必要な点に着目したり、全体のバランスが崩れたりして、安定した状態を得るまでにスコアがかえって落ちてしまう。いわゆる「スランプ」の状態である。しかし、試行錯誤の果てにようやく安定的な状態にたどり着くと、詳細な言葉の必要性が薄くなる。無意識に行動できるようになり、記録には「大雑把に、全体を見る」言葉が増えていく。スコアが良くなるのは、こういう「こつ」をつかんだ状態なのだ。
したがって、詳細な部分に意識がいってしまうことで陥る「スランプ」は、のちの安定的なシステムを生み出す必要悪である。いったん「こつ」を掴んでレベルアップすると、また詳細への意識が向いて「スランプ」の状態になる。こうして、「スランプ」と「こつ」を繰り返しながら、人は熟達していくのである。
これは、教室における教師の熟達プロセスそのものでは?
この本が僕にとって面白かったのは、第一に、「スランプと安定」をくりかえすこの熟達のプロセスの話があったから。考えてみると、「文章を書くこと」だって、この身体知のアナロジーで取られられそう。文章を書くことも、身体を使っている。どの入力デバイスを使うか、どこで書くか、そういう環境と身体のインタラクションで書くことも成立しているのだ。そして、熟達の過程で細部に注目して一時的に下手になるということも、よくある。そして、こういうふうに捉えると、作文教育にまたちょっと違った視点ができるかもしれない。美術との共通点とかも、気になってくる。
同時に、何よりもこの話は教室における教師の熟達プロセスそのものだなあ、とも思った。教師は、教室において、その時々の生徒とのやりとりをベースにしながら、授業を進め、熟達していく。生徒の反応、教室のレイアウト、授業時間…。色々な要因で授業は成り立ち、それらの影響を体感しながら、教師は授業を繰り返していく。授業とは、身体知が満載の場なのだ。教師が様々な着眼点を持って授業を記録していくことがなぜ熟達のために重要なのか、この身体知のモデルで、僕は非常に納得できた。
そして、この本のおかげで、授業者としての僕は「スランプ」を怖がらずにすむようになれる。授業の細部に意識が向かうことで授業全体のバランスが崩れることはあるかもしれないけど、それは「こつ」を掴んだ状態への過程なのだと思って、勇気を持って踏み出すことができる。
例えば、今学期の僕はライティング・ワークショップにおいて「教師のカンファランス」にとても意識が向かっている。それは、結果として授業全体のバランスをどこか崩しているかもしれない。でもそれは、さらにもう一段上に登るための、必要な熟達のプロセスなのだ。そう思えることは、とても僕を楽にしてくれる。
ということで、出会ってよかった本でした。おすすめです!



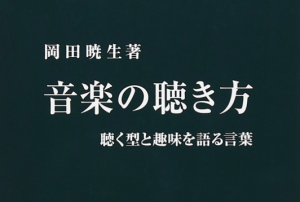
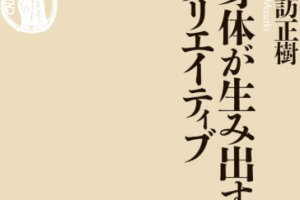
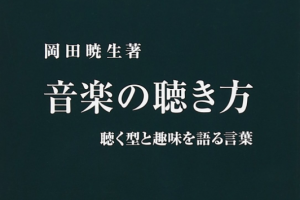




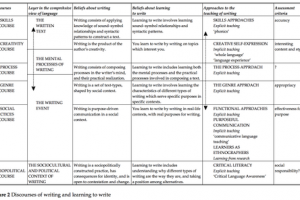
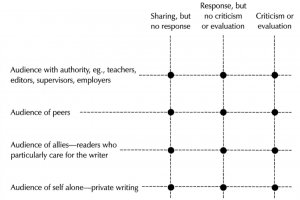





![[ITM]アトウェル、「教育のノーベル賞」候補者に](https://askoma.info/wp-content/uploads/2016/02/7efa03b5-s-50x50.png)

とても参考になる話でした。読書や作文を学生が実践している際に、どのようなことが起きているのか、またどのようなことが必要なのか、そうした学びの過程で起こることを考えさせてくれました。そして、おっしゃるとおり、教師が教える過程で起こることでもありますね。
ただし、教師の話をただ聞くだけ(あるいは写すだけ)の授業では、こうした過程は生徒(学生)では起こりえない、ということですね。生徒にも、授業において「実践知」を体得させる機会を与えるべきだということになりますね。
ありがとうございます、ぜひ読んでみてください!