この本は建築についての本だ。そんなこと、タイトルから誰だってわかる。でも、この本は、建築の世界ではまだ駆け出しとされる30代の建築家が、表現者としての自分の半生を語っている本でもある。そのありようがとても興味深く、常に「変化」を受け入れようとする著者の姿に励まされる一冊だ。僕は建築は完全な素人だけど、この本に勇気をもらった。
興味深い筆者の変容
まず読んでいて興味深かったのが、筆者の表現することへの姿勢の変容だ。筆者は高校生の時に絵画から芸術の道に入った。ところが、高校の美術の先生の薦めで通った専門学校でのレッスンを「好きなように、感じたように描きたい」筆者は受け入れられず、やめてしまう。これは、専門学校の型通りのレッスンが、筆者の自己表現の欲求を否定したように感じたからだと思う。
その後、筆者は大学で建築を学び、ドイツで4年間働き、帰国してプロの建築家の道を歩む。そして、内田樹氏の合気道の道場「凱風館」を設計し、そこで合気道を習い、その後は「顔の見えるクライアント」や工務店との共同作業で建築の仕事を行うようになる。
こうしたキャリアの中で興味深いのが、筆者が、30代から40代に移ろうとする頃になって、学校建築など、実際の利用者の顔がまだわからない「顔の見えない建築」に興味を持つようになっていくことだ。なぜなのか、そしてどうやってその建築を作るか?
やはりそのためには、普遍的なテーマを掲げた設計理論や方法論がないと、顔の見えない公共的な建築はつくれないと思っています。説明不要な建築の力を獲得する。それは、突き詰めるときっと自分自身の「身体感覚」を基準に考えることではないかと、ぼんやり感じています。個人的なはずの身体感覚は、それぞれの精度は違っていても、誰もが兼ね備えているもの。建築家が個としての身体感覚を手がかりにして、普遍的な空間へと設計をすることができれば、それは多くの人と共有可能なものになるのではないでしょうか(p.153)
ここで、筆者の個人的な身体感覚と、それに基づく自己表現が、普遍性とつながっていくのが興味深かった。おそらく、高校生の頃の筆者には、こういう感覚はなかったのではないか。もちろん、僕は別に、「高校生の頃の筆者は気づかなかったけれど、普遍的な技法を学ぶ授業にも実は意味があった」とか、そういうことを言いたいのではない。表現は、その人からしか始まらないし、技術はその人にとって意味のある適切なタイミングで渡すのが理想だ。しかし、筆者が長年かけて自己表現を突き詰めていった時に、それがやがて自己の身体感覚と他者との関わりの中から生まれ、他者に開かれていくものになっていくのが面白いと思う。
そのせいか筆者は、「縁は向こうからやってくる」という言葉をよく使う。上っ面だけだとなにやら受け身の印象をあたえるけれど、この言葉からは「積極的受容性」の雰囲気を感じる。自分の身体の感度を高め、色々な周囲の情報を自分の身体でまるごと受け入れて、まずはそこから何が表れてくるのかを見定める。だから、この著者によって「表現すること」は「受容し、自分が変化すること」でもあるのだろう。
書くことについてのフレーズいくつか
同様に印象に残るのが、書くことについての文章だ。長いのだけど、引用してみる。
そのようなとき(ライティング・ハイのような「ゾーン」に突入している時)は、得てして自分が何を書こうとしているのか、最初は「わからない」ものです。文章に限らず、スケッチやドローイングを描いているときも、本当に集中して何かを手探りで書(描)いているときは、全体像や目的地が、はっきりとはわからない状態から出発します。鮮度の高い何か得体のしれないものに触れながら、事後的に「わかる」という感覚がつかの間だけでも得られるのだと思います。そして、またわからなくなるというループ。このわからない状態から何かがわかるということそのものが創造なのではないでしょうか。自分の中でわかるということは、それを自分の中につくり出すことでもあるのです。
だから、本当に面白い文章や絵というのは、はじめに企画書や完成予想図などありません。予測不能な、どうなるかわからないところから、ついには書(描)かざるを得ない状態になり、ウズウズしながらも筆を進めることができるようになるのだと思います(p42)
これは、典型的なDiscovery Writingの文章のことだ。書くことの醍醐味がここにあると僕も思うけど、同時に、「目標」と「評価」に縛られがちな学校の作文の授業が、見落としがちなところでもある。
また、次のような文章も、書くことと読むことのとても大切な関連を捉えているように思える。
書くことに先行して、読むことが習慣化していたために、文章を書くようになってから、読書が少しずつ変化したのを今でもよく憶えています。いろんな本を読むことで、自分の知的関心が強く、深くなっていく。自分が考えた言葉にならない思いを、著者が代弁してくれているように感じたことが何度もありました。いま自分が読まなくてはならない本を本能的に嗅ぎ分けられるようになっていったようにも思います。本と以心伝心するのです。
自分の中の「わからなさ」を少しでも晴れさせたいがために、本を読むようになり、自分でも文章が書きたくなった。文章を書くようになると、もっと本が読みたくなる。
読むことと、書くことのサイクルが、次の好奇心や向上心を生み、「考える」ということが少しずつ楽しくなってきます。スケッチを「描く」ことも、本を「読むこと」や文章を「書くこと」も楽しくなるには、それなりの時間と訓練が必要ということです。
読むと書くという行為は、コインの裏表のように強く相関しています。気持ちよく文章を書いている時は、そうした先人たちによってどこか書かされているという感覚が芽生えてくるのも、とても自然なことのように思えてきます。自分というフィルターをただ通っていく感じでしょうか。(p179)
ほんと、ライティング・ワークショップとリーディング・ワークショップのサイクルをまわすことで、こうなればいいなあ、という理想の姿がここに描かれていると思う。
自分に足りないもの
さて、ここで自分の話を書くと、僕にはこの筆者のような受容的な身体的感覚、常に変化するしなやかさが足りていないのではないか、と思っている。それが、おそらく、僕の教室での場作りにも影響を与えている。僕は基本的に理屈っぽくて、ミニ・レッスンも論文を踏まえて学術的な根拠も示しながらすることが多い。個人の選択肢を増やして安心して取り組める雰囲気を作ろうとはしていても、やっぱり「学力をつける、そのために読み、書く」ことが前面に出過ぎているのかなと思う。
一方、野外のプロジェクト・アドベンチャーからライティング・ワークショップをやっているKAIさんの教室が僕にとって興味深いのは、きっとKAIさんは自分の身体を使って自然に向き合うということをなさっていて、そういう人のやるライティング・ワークショップって、僕のように「本や論文ばかり読んでいる人」のライティング・ワークショップとはかなり違うだろうと思っているからだ。
そして、自分の新境地を開拓するには、頭でっかちにならずに、自分の身体的な感覚に耳を澄ませる訓練を積むこと、じゃないかとひそかに思っている。大外れかもしれないけど(笑)
自分がそういう状況にあって、「変わらなきゃ、変わりたい」と思っているせいか、常に変化を受け入れ、場のもつ力に身体感覚を研ぎすませて自己表現を紡いでいく筆者の姿勢に、とても励まされた。もちろん、建築論として読んでも面白い。でもそれ以上に、変わろうと足を踏み出しかけている人の背中を、後ろからぐっと押してくれる本だと思う。





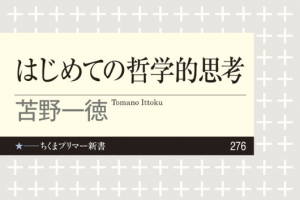
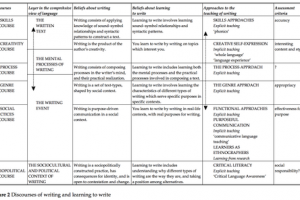
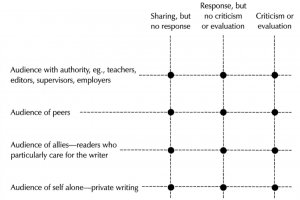
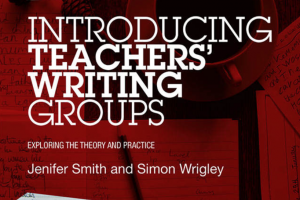








![[読書]忘れずにいたい、「子どもの見方を尊重すること」と「知識を与えること」のバランス。上野行一・奥村高明「モナリザは怒っている!?―鑑賞する子どものまなざし」](https://askoma.info/wp-content/uploads/2019/05/スクリーンショット-2019-05-09-19.55.50-50x50.png)
いろいろとすでに言葉にされているので、変わっていくように思います。そうでなくても年齢を重ねていくとおのずと力みのようなものが抜けていくようなポイントもあるように思います。だからそれまでは変わろうとムリにすることもないように思います。
そういう意味では「変わろうと足を踏み出しかけている」人の背中を「後ろからぐっと押す」必要はむしろなく、大村はまさんが言っておられるように「お釈迦様の指」みたいに相手にはわからないところでちょっと指で押すみたいなのが一番幸せな関係かも。自分で変われた感じがしますもんね。また実際に自分で変れるんだし。「教育」って促成栽培みたいでそれなりに効果はあると思うんですが、長い目でみたら、そんな必要もあんまりないような。。とも思います。目に見える成果や効率や科学性?を気にせず、どうぞ楽しんでやってくださ~い。